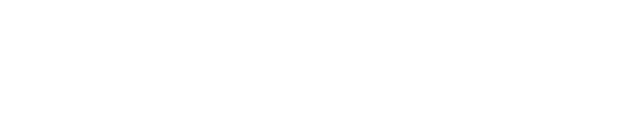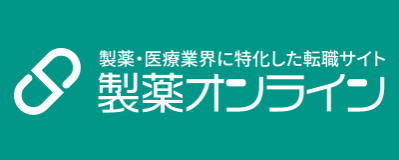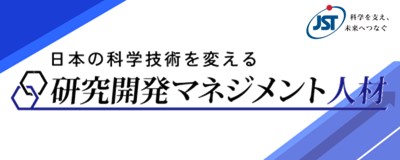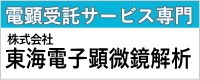フォーラム
※セッション番号について:
開催日 + フォーラム(F)+ -(ハイフン)+ 会場
(例)1F-01:第 1 日目・第 1 会場
※時間について:
各日19:15-20:30
※講演言語:フォーラムは1F-10をのぞきすべて日本語での開催となります。
1F-10のみ日本語/英語混交での開催を予定しております。
19:15-20:30
- 大気粒子・化学物質の生体影響最前線:分子生物学が紐解く新たな知見
Cutting-Edge Insights into the Biological Impacts of Atmospheric Particles and Chemical Substances: Unveiling New Findings through Molecular Biology - オーガナイザー
三村 達哉(帝京大学)、吉田 安宏(産業医科大学) -
詳 細
本フォーラムでは、「大気粒子・化学物質の生体影響最前線」と銘打ち、大気中の有害物質が引き起こす健康リスクに関する最新の研究成果を紹介する。肉眼では確認できないマイクロ・ナノ微粒子は細胞レベルでは免疫攪乱・毒性を発揮し、この細胞毒性は呼吸器、アレルギー・免疫疾患、循環器、生殖、加齢、感覚器などへの全身への生体影響を及ぼす。学会キャッチフレーズの「この指とまれ!」を掲げ、分子生物学、環境科学、医学、工学のより広い分野の専門家が一堂に会し、微粒子の脅威に立ち向かうための議論を展開する。専門家たちが語る、微粒子の脅威とその解決策への挑戦を、ぜひお聞きください。
19:15-20:30
- 撹乱に対する生物応答の多様性はどのように生まれるのだろう?
How does the diversity of biological responses to perturbations emerge? - オーガナイザー
坂井 貴臣(東京都立大学)、園下 将大(北海道大学) -
詳 細
⽣物は常に、遺伝⼦変異や環境変化など、個体の内外からの様々な撹乱に晒されている。興味深いことに、こうした撹乱に対する応答は、複数の⽣物種に共通して現れる場合もあれば、種ごとに固有のものも存在する。このような応答性の差を決定する要因の候補として、遺伝⼦や細胞型、これらの集合体である組織や器官、そしてそれらの間のネットワークが重要と推察されるが、その全貌は明らかになっていない。本フォーラムでは、こういった多様性の例を眺めつつ、どうすれば多様性の成立機序を明らかにしていけるか議論したい。
19:15-20:30
- 著者からエディターへ:日本の科学を世界へ発信する橋渡しになろう
From Author to Editor: Bridging Japanese Science to the World - オーガナイザー
岡田 由紀(東京大学)、斉藤 典子(公益財団法人がん研究会がん研究所) -
詳 細
日本人研究者の多くは「著者」として学術誌に関わっていますが、国際誌の「エディター」としての関与は極めて少なく、日本のサイエンスの国際的可視性が高まらない一因ともなっています。一方、中国などではエディターの積極的な登用や出版戦略が進んでおり、国際発信力の差は拡大しています。本企画では、国際的に著名な学術誌のエディターを招き、日本人研究者、特に若手層に対し、エディターというキャリアパスを紹介します。サイエンスの送り手としての新たな役割に目を向け、日本からの情報発信の強化に繋がることを期待します。
※本フォーラムは英語での講演を含め、日本語/英語混交での開催を予定しております。
19:15-20:30
- なぜ細胞まるごとシミュレーションが必要なのか?
Why is whole-cell simulation necessary?
協賛:自然科学研究機構 生命創成探究センター 先端共創プラットフォーム 生命体のシミュレーション - オーガナイザー
青木 一洋(京都大学)、守屋 央朗(岡山大学) -
詳 細
細胞で起きるあらゆる現象を計算機上で再現することを謳う「細胞まるごとシミュレーション」は、分子/細胞生物学の究極のゴールである。それが達成した時、私たちは細胞の生命活動を本質的に理解できたと言えるだろう。一方、何がどこまでできたらそれは達成したと言えるのか?あるいは、完成した細胞まるごとシミュレーションは何を私たちにもたらしてくれるのか? この問に対する答えは明確ではない。本フォーラムでは、研究者による話題提供と会場の参加者を加えたパネルディスカッションを通じて、今、「なぜ細胞まるごとシミュレーションが必要なのか?」(あるいはやはりそれは必要ないのか?)を改めて考える機会としたい。
19:15-20:30
- 「おもろい微生物学」を語ろう:好奇心が駆動するサイエンスの最前線へ
Let's Talk “Interesting Microbiology": Curiosity Drives Us to the Forefront of Science - オーガナイザー
片岡 正和(信州大学)、高木 博史(奈良先端科学技術大学院大学) -
詳 細
急速に進化するデジタル技術が、私たちの科学のかたちを大きく変えつつあります。微生物学の世界でも、ゲノム合成やマルチオミクスといった革新的なツールが登場し、新たなイノベーションの種が芽吹いています。本フォーラムでは、発酵や醸造のような民族の食文化に根ざした微生物機能の応用から、金属腐食のような産業課題への挑戦、さらには合成生物学による微生物の“進化”まで、幅広く「今、おもろい」話題を取り上げます。加えて、網羅的なリソースを駆使して「細胞が生きているとはどういうことか?」という根源的な問いに挑む研究もご紹介します。登壇者たちは、科学者であると同時に多彩な人生背景を持つ、まさに“選りすぐり”のメンバー。分野の垣根を越え、企業の方々も交えて、「好奇心こそが科学のエンジンだ」と思う皆さんと、一緒に語り合いたいと考えています。
19:15-20:30
- UJA留学のすゝめ2025 ~日本の科学技術を推進するネットワーク構築~
UJA Studying Abroad 2025 -Building a network to promote science and technology in Japan- - オーガナイザー
千住 洋介(岡山大学)、渡邉 友浩(北海道大学) -
詳 細
海外日本人研究者ネットワーク(UJA)は、「留学のすゝめ」と題し、さまざまな学会でフォーラムやシンポジウムを企画している。本フォーラムでは、留学経験者を講演者としてお招きし、留学生活のリアルな体験談や海外で成功するための秘訣、世界のサイエンスの現状について共有する。パネルディスカッションでは、日本人研究者が世界で活躍するための効果的なネットワーク構築について、会場からの質問に答えながら議論を深める。UJAアンケート(2019年)では、新しい時代に対応した研究への向き合い方や研究者のあり方が見えてきている。本フォーラムでは、多様なキャリアステージの留学経験者の体験談を紹介しながら、これからの時代に研究留学の効用を最大化するための議論を行う。大学院生、留学を目指す研究者、人材育成に携わる指導者の方々に向けて、ネットワーク構築やキャリアパスに関する具体的なアドバイスをいただき、日本の研究力強化と科学技術の推進を目指す。
19:15-20:30
- 分子生物学は陰謀論を超えられるか:「異端の生命科学者」この指とまれ!
Beyond 'conspiracy theories' - オーガナイザー
新田 剛(東京理科大学)、掛谷 英紀(筑波大学) -
詳 細
COVID-19の流行による世界的な混乱期には、いわゆる「陰謀論」や「異端の説」として専門家から顧みられなかった言説が多くあった。分子生物学の分野も例外ではない。新型コロナウイルスは遺伝子操作によって作られ、研究所から流出した可能性は? mRNAワクチンはCOVID-19に対する集団免疫を実現できないのでは?科学の本質は従前の知識や常識を疑い、論理的または実験的に検証し、間違いがあれば修正してゆくことにある。2025年現在、海外では「コロナ禍」の科学・医療政策や専門家の言説に対する検証や反省が進められている。米国では2020年から主流の見解に異を唱え、当時のNIH所長コリンズから「異端の疫学者」と呼ばれたバタチャリア博士がNIH所長に就任した。博士は2024年にコリンズと直接面会したとき、彼から謝罪の言葉を受けたと語っている。日本の生命科学者も腰を据え腹を割って議論すべきではないか。それこそが真の意味で公衆衛生や安全保障や健全な科学の未来のために重要であるはずだ。本フォーラムでは昨年に引き続き、COVID-19対策を生命科学の観点から検証・総括することをめざす。
19:15-20:30
- 科学者×コミュニケーター、ただいま接続中。― 生物学研究と社会をつなぐ多様なカタチ
Scientists × Communicators: Now Connecting—Diverse Ways to Link Biological Research and Society - オーガナイザー
小島 響子(名古屋大学)、岩見 真吾(名古屋大学) -
詳 細
本企画では、「サイエンスコミュニケーションにおける多様な媒体を用いたアプローチや、生物学研究と社会をつなぐ取り組みの課題・展望」にフォーカスします。研究者と科学コミュニケーターがどのように協働し、社会と生物学研究のあいだに橋を架けていくかを、聴講者とともにオープンコミュニケーションを通じて多角的に探ります。テレビ・新聞・教育・ビジュアライゼーションなどの多様なアプローチ、立場において、科学発信の最前線に立つ登壇者をお招きし、現場で直面するリアルな課題や実践知、そしてその向こうにある可能性を共有します。科学コミュニケーションとは何なのか、またその専門性はどのように定義され得るのかという根本的な問いに立ち返り、いま求められる「伝える力」や「つながる工夫」について掘り下げながら、生物学研究と社会を結ぶ連携のこれからについて考えていきます。
19:15-20:30
- 虫の会-まじめ版-12 分子生物学と昆虫学の"この指とまれ"
12th Insect meeting "Unions of Molecular Biologists and Entomologyst" - オーガナイザー
横井 翔(農研機構)、仲里 猛留(製品評価技術基盤機構) -
詳 細
昆虫は地球上で最も多様な種である。そのため、昆虫特有、それぞれの昆虫種特有の興味深い現象が多数確認されている。このような昆虫の現象は長年研究されてきたが、分子生物学的手法やシーケンサーの発達によって、これらの現象について、遺伝子、分子レベルで解明することが可能になってきた。本セッションでは、昆虫の面白い現象を研究している若手研究者に発表してもらい、分子生物学会員と一緒に議論することで、新しい研究展開ができることを期待したい。
19:15-20:30
- ゲノム言語モデルの現在と未来
Now and Future of GLM - オーガナイザー
近藤 滋(国立遺伝学研究所)、黒川 顕(国立遺伝学研究所) -
詳 細
皆さん、ChatGPTをはじめとする大規模言語モデルの“すごさ”は身に染みているはず。基本的には、読みこんだテキストを元にして、逐次的に文章を生成するAIだが、莫大な入力テキストと、膨大な計算能力と組み合わせることで、あたかも、知能が出現したかのように、どんな質問にも答えてくれる。もちろん、言語の種類は問わない。ゲノムは、デジタル記号GATCの連続が意味を持つのだから一種の言語だ。既に膨大なゲノム配列の蓄積もある。あれ、それなら、ゲノムの言語モデルを作るだけで、どんな質問にも答えられる??と思っていたら、昨年、遂にそれが出てきてしまった。(https://www.science.org/doi/10.1126/science.ado9336)
最初のバージョンにして、既に、実際の酵素よりも高活性の遺伝子配列を出力したり、ゲノム内のイントロンエクソン構造や、クロマチンの結合状態なども、ほぼ正確に予測できたりする。AIの進化スピードから考えれば、10年後、いや3年後の状態が恐ろしい。
フォーラムでは、生命科学の新しい基盤となるであろう、この新しいAI技術の現在、未来、さらには、日本の研究者がどのように対処すればよいのか、などを参加者の皆さんと議論したいと思います。
19:15-20:30
- 真核生物のユニークな分子たち ~Beyond CRISPR-Cas~
Eukaryotic Unique Molecules ~Beyond CRISPR-Cas~ - オーガナイザー
齋藤 諒(理化学研究所) -
詳 細
原核生物の獲得免疫機構CRISPR-Casを用いたゲノム編集技術は社会に大きな変革をもたらした。2013年にCas9のヒトゲノム編集への応用が示されてからここ13年の間に、次々と新しいCRISPRシステムが報告され、さらには進化的に異なるRNA誘導性システムさえも原核生物より同定されてきた。一方で、真核生物ではそのゲノムの複雑性ゆえに系統的な生物システムの探索はほとんど行われていない。 本フォーラムでは真核生物のユニークな分子と生命現象に焦点を当てる。ゲノム編集・RNA編集・転写調節ツールへの応用を“匂わせる”ものについて第一人者の先生からご紹介いただき、カビや寄生虫、さらには昆虫の持つユニークな分子と生命現象を参加者皆が賞味できる場となることを期待する。将来、、、真核生物からCRISPR-Casゲノム編集を超える技術に改変できるようなシステムは見つかるだろうか?
19:15-20:30
- 若手生物学者による異分野研究交流
Interdisciplinary summit for young biology researchers - オーガナイザー
明果瑠-安岡 いるま(大阪国際がんセンター研究所)、青木 遼太(東京大学) -
詳 細
本フォーラムは、分野横断的な学術研究に焦点を当てる。具体的には、異分野から着想を得て打ち出された研究について議論し、最新の知見や技術を共有することで、研究分野の更なる発展と新学術領域の創出を目指す。研究アプローチが多様化する昨今、興味対象や目的が本質的に同じであっても、材料や手法が異なるだけで異分野として隔てられ、閉鎖的な議論を余儀なくされる場合がある。次代を担う若手研究者には、独創的で意義のある研究課題を創出・遂行する能力が必須であり、一元的な知識体系や分野だけでは十分に研究を展開できない可能性がある。このような諦観的な現状に一石を投じるべく、国内有数の大会規模と研究分野の多様性を誇る日本分子生物学会年会を通じて、学際的な研究課題について横断的に議論し、新学術領域を独創する端緒を開きたい。
19:15-20:30
- クライオ電顕ネットワーク・ユーザーグループミーティング
Cryo-electron microscopy network user group meeting
協賛:AMED-BINDS - オーガナイザー
阿部 一啓(北海道大学)、寿野 良二(関西医科大学) -
詳 細
クライオ電子顕微鏡解析技術の目覚ましい進歩によって、構造生物学は大きな発展を遂げた。今やクライオ電子顕微鏡装置は世界中に導入され、日々新しいタンパク質の立体構造が解き明かされている。さらに細胞や組織内のタンパク質をそのまま構造解析するin situ構造解析の発展も期待されている。日本国内では、クライオ電子顕微鏡解析を支援するため、AMED生命科学・創薬研究支援基盤事業(BINDS)の支援システム“クライオ電顕ネットワーク”が存在し、国内に整備されたクライオ電子顕微鏡装置を利用できる環境が整っている。これによって、これまでタンパク質の構造解析を行ったことのない研究者であっても、クライオ電子顕微鏡を用いた構造解析に取り組むことができる。本フォーラムでは、既存ユーザーや今後利用を考えている研究者へ最先端の取り組みを紹介するだけでなく、アンケートを通して、また会場においても、ユーザーグループ、クライオ電顕施設側への要望や幅白い意見を取り入れる場を設け、日本のクライオ電子顕微鏡を取り巻く現状について多角的な議論を行う。
19:15-20:30
- 化学視点からのアミロイド研究の新戦略
New Strategies for Amyloid Research from a Chemical Perspective - オーガナイザー
末武 勲(神戸女子大学)、北條 裕信(大阪大学) -
詳 細
アミロイド病はアルツハイマー病をはじめとする神経変性疾患と深く関わっており、その発症機構の解明は重要な課題である。本フォーラムでは、アミロイド線維形成における分子レベルでの病態理解に向けた最新の研究成果を紹介する。具体的には、天然物による線維化抑制作用の評価(末武)、化学合成を用いた翻訳後修飾がタンパク質凝集に及ぼす影響に関する検討をおこなった結果(北條)、さらにde novoペプチドによる標的特異的相分離制御(池之上)について紹介する。また、量子ビームを用いたアミロイド線維の毒性の強さと原子・分子レベルにおける構造動態の相関解析 (松尾)、疾患の病態生理を作り出す最新のin vivo研究(松本)についても紹介する。これらの研究は、アミロイド病の根本的理解および治療戦略の確立に資することが期待され、多くの研究者と活発な議論ができることが期待される。
19:15-20:30
- いま臨むゲノムの景色:「和」の心と匠の技
Approaching the Genomic Horizon: The Heart of Wa and the Skill of Takumi - オーガナイザー
工樂 樹洋(国立遺伝学研究所)、白澤 健太(かずさDNA研究所) -
詳 細
高精度ロングリードシークエンスの普及は、ヒトや実験生物だけでなく、日本を象徴する野外の多様な生物種の全ゲノム情報解読をも可能にしつつある。しかし、それを達成するためには単なるDNAの扱いだけではなく、タンパク質との複合体としてのクロマチンやそれを納める核や細胞についての理解や技術、そして配列情報を正しく解釈するスキルが欠かせない。本フォーラムでは、世界で加速する生物多様性ゲノミクスの流れを汲んで、それに資する分子生物学・細胞生物学に基づく技術や解析手法について、とくに「どこにも書かれていないノウハウ」に光を当てて議論する。
19:15-20:30
- ゲノム合成と倫理-基礎研究における社会との対話の可能性を探る-
Genome Synthesis and Ethics: Exploring the Possibility of Dialogue with Society in Basic Research
協賛:JST-RISTEX 「ゲノム倫理」研究会 - オーガナイザー
田川 陽一(東京科学大学)、見上 公一(慶應義塾大学) -
詳 細
科学が社会との対話を進め、良好な関係を築くことが求められるようになって久しい。生命科学でもゲノム科学や幹細胞研究などを中心として、そのような対話の活動が積極的に進められてきた。しかし、医療や食品などの形で人々の生活に直接影響を与えることを目指した応用研究に比べると、基礎研究の場合はその意義を社会に理解してもらうことのハードルは高い。それでも、そのような活動を行なう必要性は年々高まっている状況がある。そこで、本フォーラムでは、JST CREST「ゲノム合成」領域とJST RISTEX「ゲノム倫理」研究会が連携して行ってきた、研究の倫理的・法的・社会的側面(ELSI)の論点の抽出および社会との対話の取り組みについて、その中心にいた研究者の視点から振り返る。実際の経験を通じた気づきだけでなく、その過程で抱いた楽しさや不安、不満なども併せて共有することで、今後より多くの研究者が社会との対話に一歩踏みだすための後押しをしたい。