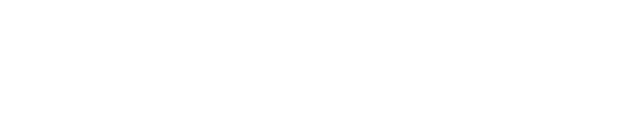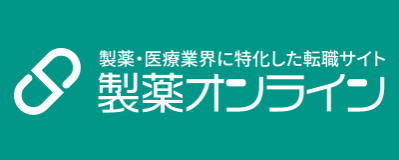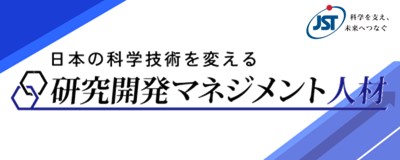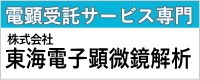公募シンポジウム
シンポジウム テーマ一覧
※公募企画 と記載のあるシンポジウムでは、一般演題から複数演題を採択予定です。
※セッション番号について:
開催日 + 午前 / 午後 (A / P) + シンポジウム(S)+ -(ハイフン)+ 会場
(例)1AS-01:第1日目・午前・第01会場
※時間について:
(午前)9:00-11:00、(午後)14:20-16:20
※講演言語について:
E 英語 J 日本語
9:00-11:00
- 異分野融合が拓くマルチオミクス生命科学の新機軸:生命システム理解から分子デザインまで
New Directions in Multiomics Life Sciences via Interdisciplinary Integration: From Molecular Design to Living Systems Understanding - オーガナイザー
島村 徹平(東京科学大学)、大澤 毅(東京大学) -
詳 細
生命科学は今、革新的な計測・解析技術の目覚ましい進展により、未踏の知見領域を切り開きつつある。一細胞レベルでのマルチオミクス解析による分子メカニズムの精密な解明から、空間トランスクリプトームによる生体組織の立体的構造理解、さらにはAIと進化工学を融合させた革新的な分子設計の確立まで、生命科学は歴史的な転換期を迎えている。本シンポジウムでは、一細胞解析・空間オミクス・マルチオミクス・合成生物学・AI技術という最先端技術の有機的な融合を通じて、生命システムの階層的な理解に挑戦する新進気鋭の研究者たちが一堂に会し、分子から個体に至るマルチスケールな生命現象の最新知見を紹介する。本シンポジウムを通じて、次世代を担う若手研究者たちの参画を促し、本分野の更なる発展への確かな礎を築くことを目指す。
9:00-11:00
- トランスポゾンと宿主:共生、進化、そして今後の発展性
Transposons and Hosts: Symbiosis, Evolution, and Prospects - オーガナイザー
塩見 美喜子(東京大学)、岩崎 由香(理化学研究所)詳 細トランスポゾンは、ヒトゲノムの約40%を占めると見積もられていた。しかし、Telomere-to-Telomere(T2T)コンソーシアムの最近の成果により、その割合は53%に達することが明確になった。この成果は、数億年にわたるヒト(宿主生物)とトランスポゾンの「奇妙な」共生関係の実態をあらためて浮き彫りにし、トランスポゾン研究の新しい時代を切り開いた。トランスポゾンによるゲノム侵入の真の目的は何なのか?我々宿主は、どのようにトランスポゾンの利己的性質を受け入れ、制御し、さらには自らの利益としようとしているのか?また、創薬の新しいモダリティとしての可能性を秘めているのか?本シンポジウムでは、トランスポゾンを多角的に眺め研究する国内外の専門家が一堂に会し、最先端の知見を共有、議論する。
9:00-11:00
- 多細胞のロバストネスを再考察する
Multicellular Robustness revisited
共催:学術変革領域研究 (A)「多細胞生命自律性」 - オーガナイザー
石谷 太(大阪大学)、井垣 達吏(京都大学)詳 細多細胞システムは、多様な撹乱を乗り越えて同じ形と機能を備えた構造体を再現よく作り出す能力「ロバストネス」を備える。約80年前にワディントンにより提唱されたこの概念は、システム生物学的手法などによる細胞内レベルの研究が進められてきたが、個体発生や疾患・老化防御を理解する上で必須な多細胞レベルでの理解は遅れている。本シンポジウムでは、独自視点から多細胞ロバストネスの本態に挑む研究者が最新データを共有・議論することで、ロバストネスを再考察したい。
9:00-11:00
- RNAエピコードの生理機能解明とその制御
Physiological functions of RNA Epicodes and their regulation - オーガナイザー
齋藤 都暁(国立遺伝学研究所)、小川 亜希子(東北大学)詳 細mRNA、tRNA、rRNAなど多様なRNA種に見出されるRNA修飾は、核酸に新たな化学的性質を付加する。その多くはゲノムが規定する情報に新たな階層のエピジェネティックコードを付加し、その異常は神経障害、癌などの様々な疾患に繋がることが明らかとなっている。本シンポジウムではこれをRNAエピコードと呼称し関連研究者を集め、分子制御メカニズム、生理機能、検出技術、医薬品応用など多角的な視点で議論し、次世代研究の展望を探る場としたい。
9:00-11:00
- 発生過程におけるゲノム継承
Shaping genome and embryo during development - オーガナイザー
坪内 知美(自然科学研究機構)、大字 亜沙美(理化学研究所)詳 細発生過程では、盛んな細胞増殖と細胞運命決定が同時に進行することで個体形成が実現する。細胞の未分化性維持や運命決定に関わるシグナリング経路の分子基盤は解明が進む一方、そのプロセスがゲノム保持と継承に与える影響は未解明な点が多い。本シンポジウムでは、同じゲノム情報を持ちながら細胞の形質に応じて巧みに制御されるゲノム継承のメカニズムについて、発生やゲノム恒常性に携わる研究者が一堂に会し、議論を深めたい。
9:00-11:00
- 細胞間の物質輸送や細胞間接着を介した相互作用に依存した細胞集団の動態制御
Regulation of Cellular Collective Dynamics Dependent on Intercellular Material Transport and Adhesion-mediated Interactions - オーガナイザー
末次 志郎(奈良先端科学技術大学院大学)、竹田 哲也(岡山大学)詳 細細胞は集まり個体を形成する。同種の細胞は集合し、接着分子を介した細胞間接着がシグナル伝達を担う。さらに、細胞突起、トンネリングナノチューブ、細胞外小胞などの膜構造による物質伝達も重要である。これらの膜構造構築による細胞の集合には細胞の形態形成が不可欠である。本シンポジウムでは細胞間接着、形態形成、シグナル伝達の分子機構を議論し、細胞集団を構成する細胞の相互作用を探る。
9:00-11:00
- 生物の栄養適応システム
Nutritional adaptation systems in multicellular organisms - オーガナイザー
岡本 直樹(筑波大学)、小幡 史明(理化学研究所)詳 細生物には栄養状態の変化に柔軟に適応できるシステムが備わっている。本シンポジウムでは、昆虫から哺乳類まで多様な生物を用いて研究している若手研究者が一同に会し、生命活動の根幹を支える栄養適応システムに関する最新の知見を持ち合うことで、生物が持つ栄養適応戦略の統合的な理解を目指す。
9:00-11:00
- ゲノム機能データとデータベースが駆動するゲノム科学
Advancing genome biology through functional genomics data and databases - オーガナイザー
川路 英哉(東京都医学総合研究所)詳 細ゲノム多様性やエピゲノム、トランスクリプトームといったゲノム機能・構造に関する様々な側面の解明がハイペースで続いており、これらは先端的な測定・解析技術および基盤として用いられるデータベースによって支えられています。本セッションでは、この分野における最新の研究とそこから得られたゲノムに関する知見について議論します。
9:00-11:00
- 「プログラムされたストレス」が駆動する真核生物の成長・発生戦略
Growth and developmental strategies driven by "programmed stress" in eukaryotes - オーガナイザー
大谷 美沙都(東京大学)、亀井 宏泰(金沢大学)詳 細真核生物は転写・転写後調節や代謝制御といった多層的な制御ステップを介して、環境に合わせて成長や発生を調整し、自らのフィットネスを向上させる。こうした成長戦略はときに種特異的である一方、系統的に大きく異なる生物種間で類似のメカニズムが見出されることもある。本シンポジウムでは、さまざまな生物種を研究材料とする研究者からの話題提供を元に、真核生物に深く根ざした発生・成長制御のコア要素としての「プログラムされたストレス」に注目し、真核生物の成長戦略の真髄を議論する。
9:00-11:00
- 核の「かたち」が変わるとき
The Changing shape of the cell nucleus - オーガナイザー
山中 総一郎(東京大学)、大杉 美穂(東京大学)詳 細本シンポジウムでは「細胞核の変形」に関連した研究結果を幅広く紹介する。Closed mitosisをする生物は細胞周期に伴ってその核の形がダイナミックに変形する。また、Open mitosisを行う生物においても細胞分裂異常が核の形成異常につながることがわかってきた。上記の例に加えて、神経細胞・生殖細胞・受精卵の分化や、老化・がん化においても核が様々にその形を変えることが知られている。そこで本シンポジウムでは、「核の形」に関連した研究発表を通して、「どんなときに核の形が変わるのか」、「核の形が変わると何が起きるのか」に関する理解を深めることを目的とする。
9:00-11:00
- 実装を目指す発生・分化・再生における細胞運命研究の新潮流
New Trends in Cell Fate Research in Development, Differentiation, and Regeneration toward Implementation - オーガナイザー
松本 征仁(順天堂大学)、岩槻 健(東京農業大学)詳 細「細胞運命変換」をキーワードに、発生、分化、再生医療、ゲノム編集技術など、生命現象における細胞運命のダイナミクスとその実用化の可能性を深掘りします。神経、消化管や膵内分泌細胞の分化や代謝細胞の運命決定、さらにはオルガノイド技術を用いた機能性臓器作成の進展、最新のゲノム編集技術を活用したin vivo遺伝子治療法の開発や、バイオイメージング技術を駆使し、血管との相互作用の重要性など、どのように細胞運命のダイナミクスに焦点を当てて最新の知見を紹介します。再生医療や疾患治療へのダイレクトリプログラミング技術導入など革新的なアプローチについても議論し、次世代型の社会実装の可能性を提案します。細胞運命変換の理解が、新たな治療法の開発に繋がる未来の鍵であることを強調し、幅広い分野での応用に向けた視点で多角的に論議し、これまでの枠組みを超えた新たな境界領域の発展のきっかけとなれば幸いである。
9:00-11:00
- 組織間相互作用を駆使した多彩な生存戦略
Diverse Survival Strategies Driven by Inter-Tissue Interactions - オーガナイザー
山川 智子(茨城工業高等専門学校)、大澤 志津江(名古屋大学)詳 細組織・個体レベルでの解析技術の進展により、従来の常識を覆す多細胞コミュニティーの動作原理が明らかになりつつあり、組織間相互作用を通じた形態形成や恒常性維持の制御機構が大きく注目されている。本シンポジウムでは、独自開発の手法を駆使して組織間相互作用の解明に挑む研究者を招き、多細胞システムの制御メカニズムやその破綻による疾患発症メカニズムについて、最新の知見と今後の展開を議論する。
9:00-11:00
- ケミカルホメオスタシス:化学パラメーターで紐解く細胞内恒常性
Chemical Homeostasis: Unraveling Cellular Homeostasis through Chemical Parameters - オーガナイザー
潮田 亮(京都産業大学)、河野 恵子(沖縄科学技術大学院大学)詳 細細胞内恒常性は生命特有の驚異的な頑強性としなやかな柔軟性を併せ持ち、一見相反するような多面的特性を有している。この複雑な多面性こそが生命の理解をより困難なものにしていると言ってよいだろう。本シンポジウムでは、プロテオミクス解析、高解像電子顕微鏡、深層学習など最新技術を駆使し、化学パラメーターに基づいて、細胞内恒常性の持つ多面性をより明確化することに挑戦する。分子から個体まで多階層にわたる化学パラメーターを集約し、老化や疾患研究への応用まで議論したい。
9:00-11:00
- ストレス応答:分子~生命体の視点から
Stress responses from molecules to organisms - オーガナイザー
池田 史代(大阪大学)、永田 理奈(京都大学)詳 細様々なストレス刺激への細胞内および生体反応について、分子メカニズム、細胞内シグナル、動物モデル、疾患といった広い視点から理解を深める。
9:00-11:00
- 遺伝子発現制御研究の最先端と新展開
The Frontiers and New Advances in Gene Expression Regulation Research - オーガナイザー
笹井 紀明(奈良先端科学技術大学院大学)、藥師寺 那由他(理化学研究所)詳 細動物の遺伝子発現制御は、シグナル伝達経路や転写因子に加え、クロマチン制御、転移因子、3次元ゲノム構造など、多様な仕組みで成り立っている。この制御機構は、胚発生や老化、疾患発症の生物学的プロセスに関与するだけでなく、種固有の制御機構は生命進化にも寄与してきた。本シンポジウムでは、in vitroおよびin vivoのアプローチで、生物学的現象の解明や制御機構の破綻による病態の理解を目指している研究者らが集まり、遺伝子発現制御機構の多様性や今後の展望について議論したい。
9:00-11:00
- 血管周囲細胞の疑問に挑戦する―残されたフロンティアへの情熱―
Challenging to the questions in perivascular cells - Passion for the Remaining Frontiers- - オーガナイザー
山本 誠士(富山大学)、榎本 篤(名古屋大学)詳 細血管は、血管内皮細胞の外側にペリサイトや線維芽細胞などの血管周囲細胞が存在し微小環境を構成している。血管周囲細胞は、ECM産生やシグナル分子を精妙に制御し、臓器特異性や物理的強靭性を発現すると考えられている。しかしながら、血管周囲細胞の発生様式や分子機構については未だ議論の渦中である。本シンポジウムでは、血管周囲細胞の情熱的研究を紹介し、シニアから若手研究者とともに広く知識を共有し、残されたフロンティアとされる血管周囲細胞研究について熱く議論する。
9:00-11:00
- 健康と疾患をつなぐシングルセル制御学
Single-cell Regulome Linking Health and Disease - オーガナイザー
野村 征太郎(東京大学)、油谷 浩幸(東京大学)詳 細健康と疾患の境目はどこにあるのか?細胞の集合体である個体を維持するために、臓器において個々の細胞はどのように生まれ変わり、そしてどのように他の細胞と連携して機能を生み出しているのか?果たして疾患とは何なのか?何を持って疾患と呼ぶのか?シングルセル解析・空間オミックス解析・デジタルAI・イメージング・ゲノム編集・モデリング・・・近年の解析・制御技術の発展によって、生命科学研究は大きく様変わりした。これらの最先端技術を組み合わせることで「健康と疾患の境目」を見つけ、これを制御して疾患を治療できる可能性が出てきた。本シンポジウムでは、これらの技術を開発・駆使して「健康と疾患」を制御しようとする最先端研究者が一堂に会し、新しい生命科学研究の今後の方向性について皆で一緒に考えてみたい。
9:00-11:00
- 「メゾスケール構造体」:生物と無生物とを繋ぐ細胞内構造体のイメージング
“Meso-scale structure”: Imaging the border between living and non-living materials
共催:学術変革領域研究 (B):STED技術による生物と無生物をつなぐメゾスケール現象の動的解明 - オーガナイザー
米田 竜馬(埼玉医科大学)、黒澤 俊介(東北大学)詳 細顕微鏡を用いて、我々は様々な「小さきもの」を観察することが可能となった。電子顕微鏡を用いればタンパク質や核酸の立体構造を、光学顕微鏡は細胞内の様々な生命活動を観察することができる。では「タンパク質や核酸(無生物)」と「細胞(生物)」の間は?本シンポジウムでは、数十nmスケールの細胞内構造体「メゾスケール構造体」をターゲットとして、その構造や形成過程の観察方法やイメージング方法について紹介する。
14:20-16:20
- 細胞・分子から紐解く生老病死の統合理解
Integrated Understanding of Life, Aging, Disease, and Death Unraveled from the Cellular and Molecular Perspectives - オーガナイザー
田中 知明(千葉大学)、南野 徹(順天堂大学)詳 細エイジングシグナルやメタボリックストレスが織り成す複雑なネットワークは、細胞老化を超えて臓器や個体レベルの老化を形作り、多様な疾患の発症や進展に深く関与する。シングルセル解析や空間トランスクリプトミクス、プロテオミクスといった先端技術の進展により、これらのネットワークを細胞間や臓器間で動的かつ多元的に捉える新しい視点が得られている。本シンポジウムでは、神経、代謝、免疫、遺伝子の視点から生老病死のメカニズムを紐解く研究者が集い、エイジングと疾患病態の交絡と恒常性制御基盤の理解に向けた挑戦的な研究を紹介しながら、皆様と一緒に議論したい。
14:20-16:20
- CRISPR-Cas9から拡張していくノックイン技術の新潮流
The new trend in knock-in technology that is expanding from CRISPR-Cas9
共催:日本ゲノム編集学会 - オーガナイザー
大塚 正人(東海大学)、水野 聖哉(筑波大学)詳 細目的のDNA断片を標的遺伝子座位に正確に挿入する遺伝子ノックイン技術のニーズは極めて高く、それを簡便且つ効率的に行う手法の開発・改良が求められている。本シンポジウムでは、古典的な手法から最新技術まで、標的遺伝子座位に長鎖DNA断片を挿入する多様なアプローチやその関連技術について紹介する。各演者が技術の現状、利点や課題、応用例等を共有し、それぞれの手法がもたらす新たな可能性や今後の展望について議論する。
14:20-16:20
- 高分解能蛍光顕微鏡技術は分子細胞生物学領域にどのようなインパクトを与えられるか?
What impact can high-resolution fluorescence microscopy technology have on the field of molecular cell biology? - オーガナイザー
川辺 浩志(群馬大学)、岡田 康志(理化学研究所)詳 細細胞に発現するタンパク質の動態と局在を正確に把握することは、細胞の機能を理解する上で重要である。そのための技術として、空間分解能と時間分解能が高いライブイメージング技術や複数タンパク質を観察できる超解像蛍光顕微鏡技術が必要である。本シンポジウムでは、このような最先端の蛍光顕微鏡技術の原理を説明したうえで分子細胞生物学領域でのこれらの蛍光顕微鏡技術の今後の応用の可能性について議論したい。
14:20-16:20
- 生命の3ドメインから読み解く染色体ダイナミクスの普遍原理と多様性
Exploring the universal principles and diversity of chromosome dynamics across the three domains of life - オーガナイザー
竹俣 直道(立命館大学)、尾崎 省吾(九州大学)詳 細長大な染色体を折り畳み、複製し、そして次世代へ分配するプロセスはあらゆる生命に不可欠である。一方、共通の祖先から誕生したはずのバクテリア、アーキア、そして真核生物の間ではこのメカニズムに無視できないほどの多様性が存在する。本シンポジウムでは、各生命ドメインの染色体ダイナミクスに関する最新の研究成果を紹介するとともに、遺伝システムの多様性とその背後に隠された共通原理を議論する。
14:20-16:20
- 細胞集団移動が織りなす時空間秩序
The Spatiotemporal Order of Collective Cell Migration - オーガナイザー
堤 弘次(北里大学)、稲木 美紀子(兵庫県立大学)詳 細細胞の集団移動は、細胞が協調して自己組織化する過程で生じ、多細胞生物の発生、再生、がんの浸潤などで観察される。集団移動では、シグナル伝達、接着、力学的相互作用の時空間制御により秩序が形成されるが、これらを協調させる仕組み全体を掴むのは依然として困難である。本シンポジウムでは、数理モデルや三次元イメージング技術による最新の解析結果を共有し、秩序形成のメカニズムを探ることで、今後の研究の方向性を議論する。
14:20-16:20
- 金属トランスポーターの最前線:構造、機能、疾患、そして創薬
New insights into the metal transporters: structure, functions, disease, and drug development - オーガナイザー
深田 俊幸(徳島文理大学)、神戸 大朋(京都大学)詳 細金属は、タンパク質の構造維持や補酵素として機能するだけでなく、多様な生体分子の制御を介して生命維持に貢献する。亜鉛や鉄、銅、マンガンなどを輸送する金属トランスポーターの失調が疾患と関連することから、金属トランスポーターは治療標的分子としても注目されている。このシンポジウムでは、構造から機能、そして疾患の機序と創薬に至る金属トランスポーター研究の最新情報について議論する。
14:20-16:20
- ゲノム高次構造の謎に迫る:分子レベルで読み解く制御メカニズム
Mechanistic insight into the three-dimensional organization of chromosomes - オーガナイザー
Jeppsson Kristian(東京大学)、坂田 豊典(東京大学)詳 細染色体では三次元的なゲノム構造を介して、遺伝子発現、DNA複製及び修復が緻密に制御されている。本シンポジウムでは最先端のゲノム解析、1分子解析などから得られた最新の知見について紹介し、新たなゲノム高次構造制御の機構やその発生疾患との関わりについて議論する。
14:20-16:20
- モデル生物 C. elegans を活用した疾患研究
C. elegans in disease research: A versatile model organism - オーガナイザー
首藤 剛(熊本大学)、林 悠(東京大学)詳 細本シンポジウムでは、C. elegans を疾患研究のモデル生物として活用する最前線の研究を紹介する。C. elegans は遺伝学、薬理学、分子生物学の強力なツールであり、寿命や健康寿命、疾患に関連する表現型解析において重要な知見を提供する。さらに、マウスやヒトを用いた研究との融合により、疾患メカニズムの解明や新規治療法の開発が加速される。本シンポジウムでは、C. elegans 研究のメリットと今後の展望について議論する。
14:20-16:20
- 系譜と多機能性から解く線維芽細胞分子生物学
Deciphering Fibroblast Molecular Biology: A Lineage and Multipotency Perspective - オーガナイザー
仁科 隆史(東邦大学)、倉島 洋介(千葉大学)詳 細構造支持細胞として考えられている線維芽細胞は、細胞の運命決定、組織修復、さらにはがん微小環境の形成や臓器線維症の進展など、多彩な生理的・病理的プロセスにおいて中心的な役割を果たすことが明らかになってきた。この線維芽細胞の多機能性を制御する分子メカニズムの解明は、生体恒常性の理解と新規治療戦略の開発において重要な課題である。本シンポジウムでは、様々な組織常在性の線維芽細胞に加えて、異なる細胞系譜に由来する線維芽細胞の最新の研究成果を共有し、未だ多くの謎に包まれた線維芽細胞の本質的な理解を深めることを目指す。
14:20-16:20
- 細胞外環境の変化が駆動する生理機能と疾患形成のメカニズム
Mechanisms of physiological and pathological functions driven by changes in the extracellular environment - オーガナイザー
辰川 英樹(名古屋大学)、木岡 紀幸(京都大学)詳 細細胞外環境は単に細胞の足場にとどまらず、細胞機能や挙動を規定し、組織恒常性の維持や修復に重要な役割を果たす。特にECM、分泌因子、物理的環境の変化は、細胞間相互作用やシグナル伝達を通じて組織リモデリングや生理機能の制御、炎症、線維化、腫瘍進展など病態形成にも深く関与する。本シンポジウムでは、細胞外環境の変化がもたらす細胞および組織レベルでの影響に焦点を当て、最新の研究成果を共有し議論を行う。
14:20-16:20
- RNAのトリセツ ~ RNAエクサプテーションによる分子装置の機能拡張
How to use RNA : Expanding Molecular Machineries Through RNA Exaptation - オーガナイザー
中川 真一(北海道大学)、高橋 葉月(理化学研究所)詳 細生物は進化の過程で一見ガラクタのようにも思われるRNAを拾い上げ、タンパク質単独ではなし得ない機能を持った新たな分子装置を作り上げてきた。本シンポジウムでは、大規模スクリーニングによる新規機能性lncRNAの探索や変異マウスを用いた生理機能解析、さらには構造を含めた詳細な分子機能解析を取り上げ、生物がRNAを外適応(exaptation)させることでいかにして革新的な分子装置を作り上げてきたのかについて議論していきたい。
14:20-16:20
- 化学・生物学・工学・医学連携が可能にする「組織血管化」の統合的理解
An integrated understanding of “tissue vascularization” by the collaboration of chemistry, biology, engineering and medicine - オーガナイザー
水谷 健一(神戸学院大学 )、石井 - 嶋田 弘子(慶應義塾大学)詳 細血管は、生体の恒常性維持や器官形成など、全ての組織を統合するためのネットワークとして機能し、組織再生にも決定的な役割を果たす。本シンポジウムでは、発生学(神経発生・脳オルガノイド)、材料化学(天然物・合成ペプチド)、工学(マイクロ流体デバイス)、病態(脳梗塞など)の観点から組織血管化に関する最新の知見を紹介し、各々の分野の概念を融合することで、血管化が司る多様な生命現象についての幅広い議論を展開する。
14:20-16:20
- 性差を科学する:性差研究の今、そして未来
The Science of Sex Differences-Present and Future - オーガナイザー
鈴木 堅太郎(山梨大学)、溝上 顕子(九州大学)詳 細「あなたは、性を意識して研究をしていますか?」器官の大きさや性質、疾患の罹患率など、私たちには様々な性差がある。最近の研究から個々の細胞では、トランスクリプトームやプロテオームレベルで差異があり、これらの集積が表現型としての性差を形成することが明らかになってきた。本シンポジウムではこのような性差形成メカニズムを分子・細胞レベルで紐解く最新の研究を紹介し、性差研究の面白さと必要性、今後の展望について論議する。
9:00-11:00
- 神経変性疾患に対峙する基礎から応用研究の最前線
Multidisciplinary research on neurogenerative disorders - オーガナイザー
齋尾 智英(徳島大学)、奥村 正樹(東北大学)詳 細神経変性疾患の発症要因は複合的である。神経変性疾患に至る核酸やタンパク質の異常が知られるが、未だ根本治療には至っていない。本シンポジウムでは、神経変性疾患に関わる核酸・タンパク質の異常化の基礎研究から本疾患を克服する応用研究の最前線研究を紹介することで、新たな発想を誘発したい。
9:00-11:00
- 転移因子が司るゲノム制御
Genome regulation by transposable elements - オーガナイザー
木下 善仁(近畿大学)、中濱 泰祐(大阪大学)詳 細哺乳類の転移因子は、LINE、SINE、LTRレトロトランスポゾンやDNAトランスポゾンなどがある。転移因子は、遺伝的多様性を生み出し、進化的変化を促進する一方で、疾患の原因にもなりうる。転移因子がゲノム内で移動することによって、ゲノムの再編成を行うほか、遺伝子発現の調節やエピジェネティックな変化にも影響を与えうる。本シンポジウムでは転移因子が司るゲノム制御が関わる生命現象の最新知見を議論したい。
9:00-11:00
- 多細胞組織の休眠研究と技術開発の最前線
Frontiers of multicellular tissue dormancy research and technology development - オーガナイザー
高岡 勝吉(徳島大学)、本田 瑞季(広島大学)詳 細哺乳類胚の発生休止、線虫の休眠、潜伏がん、組織幹細胞などに代表される多細胞組織の見かけ上の休止は、様々な生命現象に見られる。しかしながら、従来の研究は、“発生のDiapause” “組織幹細胞のQuiescence” “がんのDormancy”など、これまで個々の分野で研究されてきた。そこで、本シンポジウムでは、多様な休眠研究者と技術開発者が一堂に会し、包括的な観点から、多細胞組織の休眠の共通性と多様性について議論する。
9:00-11:00
- 複製ストレスとロバストネス:細胞運命を司る巧妙なバランス
Replication Stress and Robustness: A Balancing Act in Genomes - オーガナイザー
塩谷 文章(東京医科大学)、高橋 達郎(九州大学)詳 細DNA複製は正確に行われる一方、「間違いを許容する」ことで進化を可能にする側面を持つ。本シンポジウムでは、細胞がクロマチン環境の変動に由来するDNA複製ストレスに適応し、修復機構やオルタナティブな複製システムを制御することで複製の頑健性(ロバストネス)を発揮するメカニズムについて議論する。また、複製頑健性が複製ストレス下で複製完了を優先させ、細胞の生存とゲノム・エピゲノムの健全性の「トレードオフ」に寄与するメカニズムについても考察する。
9:00-11:00
- RNA制御の破綻がもたらす疾患メカニズムの最前線
RNA Dysregulation and Disease Mechanisms - オーガナイザー
Morita Masahiro(University of Texas Health Science Center)、Postovit Lynne(Queen's University)詳 細RNAの翻訳・分解などの転写後制御は、細胞の恒常性維持に不可欠なプロセスであると長らく考えられてきた。しかし、近年の技術革新により、従来の概念が覆され、新たなRNA制御メカニズムが生命現象や疾患の発症に深く関与していることが明らかになりつつある。特に、特定のmRNAの選択的な翻訳や分解制御、さらには非コードRNAの機能的役割が、がんや神経疾患などの病態形成において重要であることが示されてきた。本シンポジウムでは、転写後制御の分子機構とその生理機能に関する最新の知見を紹介し、その破綻が疾患の発症や進行にどのように寄与するのかを議論する。
9:00-11:00
- in vitroで表現し、計測して理解する
Exploring Biology Through In Vitro Modeling and Measurement - オーガナイザー
服部 一輝(東京大学)、新井 健太(未来ICT研究所)詳 細生体を理解するためには、その一部をin vitroで切り出して解析する手法が有効だ。その切り出し方や測り方を工夫することで、組織・細胞・分子レベルで多様な現象を詳らかにすることができる。本シンポジウムでは、生体の一部を巧くin vitroで再現・計測する工学・光学的なアプローチの一端に触れ、in vitroの解析手法の今後の展開を議論する。
9:00-11:00
- 新たな手法に基づくオミクスデータが拓く生命科学の最前線
Omics Data Based on New Methods Opens the Frontiers of Life Science
共催:JST ライフサイエンスデータベース統合推進事業「統合化推進プログラム」 - オーガナイザー
伊藤 隆司(九州大学)詳 細新たな実験手法の出現や解析技術の発展により、生命科学研究をとりまく環境は常に大きく変化してきた。その中で公共データベースが果たす役割は大きく、これまでもさまざまな研究ニーズに応えてきた。本シンポジウムでは空間トランスクリプトミクスとロングリードゲノミクスの新たなデータベースを紹介し、これらを活用した研究アプローチが切り拓く生命科学の最前線について議論したい。
9:00-11:00
- CAR-Tから展望できるデザイナー細胞技術の新展開
Beyond CAR-T: Pioneering New Horizons in Designer Cell Technology - オーガナイザー
石井 秀始(大阪大学)、原 知明(大阪大学)詳 細キメラ抗原受容体(CAR)T細胞療法は、細胞に新たな機能を付与し、さまざまな疾患の治療に応用する技術として、再生医療と遺伝子治療が融合する領域で注目されています。薬価収載されたCAR-T細胞療法は劇的な効果を示す一方で、依然としていくつかの課題が残されています。本シンポジウムでは、CAR-T療法の成果を基盤とし、細胞の標的化技術や新たなシーズの開発に焦点を当て、これを超える新技術の臨床応用に向けた最新の知見を共有・議論し、分子生物学技術の医療応用を促進します。
9:00-11:00
- 腸内デザイン学の社会実装化に向けた超学際研究
Transdisciplinary research for social implementation of the Gut Design study - オーガナイザー
佐々木 伸雄(群馬大学)、福田 真嗣(慶應義塾大学)詳 細腸内環境の撹乱は様々な疾患発症の素因となるため、腸内細菌叢を制御する技術(腸内デザイン)の開発が期待されている。高次複雑系を構成している腸内細菌叢を自在に操作するためには学際融合研究が求められる。そこで本シンポジウムでは、腸内細菌叢学を基盤とし、バクテリオファージ生物学やそれらを活用した医療、さらにはシステム生物学や代謝学など、多様な分野で活躍する研究者の技術基盤を共有していただくことで、腸内デザイン学が挑むべき領域について議論したい。
9:00-11:00
- 超世代的生物学
Transgenerational Biology: DOHaD theory revisited - オーガナイザー
根本 崇宏(日本医科大学)、栃谷 史郎(鈴鹿医療科学大学)詳 細「発生初期の望ましくない環境が将来の疾患感受性に影響する」とのDOHaD学説が広く認知されるようになってきた。さらに、環境による疾患感受性の変化は子孫にまで影響を残すことが明らかとなりつつあるが、環境による疾患感受性の変化と世代間伝搬のメカニズムには不明な点が多い。そこで、「環境により疾患感受性の変化が生じる分子機序とその世代間伝搬」をテーマに、若手・中堅の研究者と議論する。
9:00-11:00
- GTP生物学の進歩
Advances in GTP biology - オーガナイザー
竹内 恒(東京大学)、佐々木 敦朗(University of Cincinnati College of Medicine)詳 細GTPは特定の細胞機能を駆動するエネルギー物質との理解を超え、セカンドメッセンジャーのように細胞内代謝とシグナル伝達を積極的に制御することがわかってきた。細胞内では現パラダイムでは説明できない濃度勾配を形成し時空間的制御を受ける。高等動物ではGTPは細胞間さらには生体レベルでも外的環境に応じた代謝制御を担い、がんやウイルスの増殖にも影響する。そのためGTP代謝は重要な創薬標的であり、その進化は生命の可能性を広げた。本シンポジウムではGTP生物学の進展を技術的進歩とともに議論する。
9:00-11:00
- 光生物学:可視光線と紫外線への生物学的応答
Photobiology: Biological Responses to Visible Light and UV Radiation - オーガナイザー
川澄 正興(University of Washington)、He Yu-Ying(University of Chicago)詳 細光生物学は、光と生命とのかかわりを探求する学問である。異なる波長の光が及ぼす生物学的影響は多岐にわたるが、紫外線による遺伝子変異が皮膚がんにつながることはよく知られている。近年の技術進歩により、可視光線と紫外線照射に対する細胞の様々な応答(DNA損傷と修復、酸化ストレス、遺伝子発現、光受容、シグナル伝達、炎症、免疫、細胞周期への影響)が、分子レベルで解明されてきた。本シンポジウムでは、光生物学の最先端の研究を紹介する。
9:00-11:00
- 動物が示す多様な生得的社会性行動の分子神経基盤
Molecular neurobiology of innate social behaviors: environments talk with genes - オーガナイザー
佐藤 耕世(情報通信研究機構)、苅郷 友美(ジョンズホプキンス大学)詳 細動物が示す性行動や攻撃行動、養育行動などの社会性行動は、生得的でありながら様々な内的・外的要因に応じ柔軟に変化し、個体の環境適応や世代交代に重要な役割を果たしている。本シンポジウムでは、環境や経験がどのように脳に作用し、行動や心理特性の変容をもたらすのかについて、様々な動物種を用いた最新の研究を紹介し、その分子・神経生物学的基盤の理解の深化を図る。
14:20-16:20
- 幹細胞合成生物学
Synthetic Stem Cell Biology - オーガナイザー
谷内江 望(The University of British Columbia)、Cantas Alev(京都大学)詳 細合成幹細胞生物学は、幹細胞生物学とバイオエンジニアリングにおけるアプローチを統合することで、動物体内における細胞や臓器の動的かつ多様なふるまいを捉えようとする、新しいエキサイティングな研究分野である。 幹細胞由来の臓器モデルや発生モデルおよびそのエンジニアリングは、生物学における新たなリソースとなり、これらのモデルが多様な大規模データの計測を可能にしたことは、ゲノムプログラムを解釈するAIベースの生物学が近年登場したこととタイミングが合っている。 本シンポジウムでは、国内外の第一線で活躍する科学者たちが、最新の研究成果を共有する。
14:20-16:20
- 真核生物における翻訳が制御する生命現象・疾患
Eukaryotic translation regulates various biological processes and human diseases - オーガナイザー
藤原 俊伸(近畿大学)、山下 暁朗(琉球大学)詳 細高等真核生物においてmRNA翻訳制御は様々な生命現象において重要な役割を果たしている。翻訳に関わる分子の遺伝子変異や異常がヒト遺伝性疾患や神経変性疾患などの原因となることも明らかになりつつある。本シンポジウムでは、ストレス応答やリボソーム衝突、tRNA修飾などによる翻訳制御を、リボソーム高解像度Cryo-EM構造解析、トランスレートローム解析などの方法論を用いて解明した最新の研究成果を紹介する。
14:20-16:20
- 染色体の多様性がもたらすインパクト
Exploring Chromosomal Diversity: Impact and Significance - オーガナイザー
趙 民知(がん研究会 がん研究所)、松本 知訓(大阪大学)詳 細細胞分裂の制御異常は、染色体の不分離や転座、欠損といった多様な構造的および数的変化を引き起こす。こうした染色体の多様性は、遺伝子発現や細胞周期を変動させ、細胞の新たな形質の獲得を促進し、細胞の多様化や老化、がん化に寄与することが知られている。本シンポジウムでは、細胞レベルから組織・個体レベルに至るまで、染色体の多様性が及ぼす影響を包括的に理解し、最新の研究成果を統合することで、その生物学的意義を多角的に議論したい。
14:20-16:20
- RNA治療薬の可能性を拓く:基礎研究から臨床応用への展望
Unlocking the Potential of RNA Therapeutics: Perspectives from Bench to Bedside - オーガナイザー
谷 英典(横浜薬科大学)、秋光 信佳(東京大学)詳 細RNA治療薬は、従来の医薬品では治療困難だった疾患に対する革新的なアプローチとして注目を集めている。本シンポジウムでは、RNA生物学の最先端研究から、実用化に向けた課題、そして臨床応用の最新成果まで、第一線の研究者が一堂に会し議論する。RNA医薬の設計・デリバリー技術の進展、新規標的疾患の開拓など、この急速に発展する分野の全貌に迫り、RNA医薬が拓く未来の医療を、共に探求する。
14:20-16:20
- ライフステージにおける組織恒常性の変化
Changes in tissue homeostasis across the lifespan - オーガナイザー
一條 遼(京都大学)、佐田 亜衣子(九州大学)詳 細組織の恒常性は生涯にわたってさまざまに変化する。我々の組織はその変化に柔軟に対応するが、組織恒常性の破綻によりがん、線維化、老化が誘導される。本シンポジウムではライフステージにおける変化に対し、組織、細胞がいかに応答するかについて、さまざまな視点から議論したい。
14:20-16:20
- ストレスや薬物依存行動を司どるエピジェネティック遺伝子発現メカニズム
Epigenetic and transcriptional mechanisms of Stress and Substance Use-induced behavioral adaptations - オーガナイザー
谷口 誠(Medical University of South Carolina)、内田 周作(名古屋市立大学)詳 細ストレスやコカイン、ヘロインなどの薬物使用の経験は、神経可塑性を引き起こし、気分障害や薬物依存症に関連する病的な行動変化を誘発する。近年の研究では、これらの病的行動変化における遺伝子発現やそのエピジェネティック遺伝子発現調節の役割が注目されている。本シンポジウムでは、細胞種および回路特異的な遺伝子発現の変化、クロマチン構造、エピジェネティック調節因子、さらに長鎖ノンコーディングRNAを介した機構について、薬物依存症やストレスによる気分障害における役割を議論します。
14:20-16:20
- サンゴ礁保全へ:環境遺伝子解析が開く環境動態研究の新境地
Toward coral reef conservation: Environmental gene analysis opens new frontiers in environmental dynamics research - オーガナイザー
米澤 遼(東京大学)、安田 仁奈(東京大学)詳 細サンゴ礁生態系はサンゴと多彩な微生物の共生で維持されるが、分子レベルの相互作用やは未解明な点が多い。本シンポジウムでは、環境エクソソーム解析や環境RNA、環境RNA分子ロボットなどの新手法を用い、海洋生物由来のRNA-seqを可視化し、生物間相互作用の解明とともに非侵襲的なストレス検出手法を開発する。得られた知見をもとにサンゴ礁保全への予測と対策を議論する。
14:20-16:20
- DNA複製とゲノム・染色体構造のダイナミクス
Dynamic regulation of DNA replication and genome/chromosome organization - オーガナイザー
平谷 伊智朗(理化学研究所)、鐘巻 将人(国立遺伝学研究所)詳 細DNAの二重らせん構造が即座に半保存的DNA複製を予見したように、DNA複製とゲノム・染色構造は切っても切れない関係にある。近年、この関係性が、メガベース単位のクロマチンドメインレベルに至るまで成り立っており、多様な染色体機能と関連していることが明らかになってきた。本シンポジウムでは、様々な角度やスケールでこの課題に取り組んでいる気鋭の演者をお招きし、研究の現在地を俯瞰する。
14:20-16:20
- アカデミア創薬会議 2025
Academic Drug Development Conference 2025 - オーガナイザー
池田 幸樹(京都大学)、井上 喜来々(大阪公立大学)詳 細アカデミア創薬が浸透してきた昨今、アカデミア初のシーズが数多く発信されている。しかし、シーズ件数に対して1%程度の共同研究しか生まれていないのも事実である。このギャップは両者の創薬に対する意識によるものが大きい。この溝を埋めるために注目されているのが、ニーズ=患者の声、である。ニーズに寄り添い、お互いをリスペクトし手を取り合って開発を進める体制を構築しなくては困難な病気に打ち勝つことは難しい。本会議では医療ニーズに立脚した医薬品や技術の開発などに注目して議論を深め、アカデミアと企業が共創できる創薬の道を探る。
14:20-16:20
- 代謝レジリエンスの老化変容とその修復機構
Aberrant metabolic resilience as aging mechanisms - オーガナイザー
近藤 祥司(京都大学)、田久保 圭誉(東北大学)詳 細高齢やフレイルでは「レジリエンス(回復力・予備能)」が低下し、日常生活の段階的な衰えや複数疾患罹患の原因となる。老化個体で蓄積する老化細胞由来の炎症因子放出SASPはレジリエンス低下を誘導する。レジリエンスの修復を目的として、老化治療が提唱される。代謝レジリエンスもその一つであり、その最新の知見を発表・議論する。
14:20-16:20
- 構造生命科学の新展開 -ダイナミクスからin situまで-
Advances in Structural Life Science: From Dynamics to In Situ - オーガナイザー
西増 弘志(東京大学)、加藤 英明(東京大学)詳 細クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)における様々な技術革新により、我々は様々な生命現象を原子レベルから理解するのみならず自然界に存在しないタンパク質のデザインまでも可能になりつつある。本セッションではcryo-EMを用いたタンパク質や核酸のダイナミクス解析やin situ解析、そうした技術を活用した新規タンパク質の開発など、最新の研究成果を中心に発表・討論を行いたい。
14:20-16:20
- 代謝が解き明かす体質の科学
The Science of Constitution Revealed by Metabolism - オーガナイザー
本村 泰隆(東京理科大学)、柳川 享世(東海大学)詳 細アレルギーの発症しやすさや太りやすさといった「体質」は、曖昧な概念であり、その本質は依然として十分に解明されていない。しかしながら、体質は疾患の根幹に関与し、発症要因の一つと考えられることから、その解明は喫緊の課題となっている。近年、代謝の観点から体質の実態が徐々に明らかになりつつある。本シンポジウムでは、各分野の専門家を招き、最新の研究成果を紹介するとともに、多角的な視点から体質の理解を深める。
14:20-16:20
- ペルオキシソーム研究の最前線~70年の歩みとこれからの展開~
The frontier of peroxisome research ~70 years of progress and future developments~ - オーガナイザー
山下 俊一(九州大学)、杉浦 歩(順天堂大学)詳 細ペルオキシソームは真核生物のほぼ全ての細胞に存在するオルガネラであり、極長鎖脂肪酸のβ酸化やエーテルリン脂質の生合成など重要な代謝を担っている。1954年に初めてペルオキシソーム構造が発見されて以来、その生合成、代謝、分解機構の分子基盤が次々と報告され、生体内における重要性が明らかにされてきた。本シンポジウムではペルオキシソーム研究を世界的に牽引する研究者が一堂に会し、最新の知見を紹介するとともに、今後の更なる展開を議論する。
14:20-16:20
- 多細胞システムのための場の設計・制御
Design and control of biomimetic system for multicellualr organization
共催:学術変革A マルチモダルECM - オーガナイザー
萩原 将也(理化学研究所)、鳴瀧 彩絵(東京科学大学)詳 細細胞は周囲環境から様々な力学・化学的シグナルの空間情報を受け取り、多細胞システムを構築している。 このシステムのメカニズム解明や再構築を行う上で、人為的に場を操作する技術は非常に有用である。 一方、これら技術を有効的に多細胞システムに活用するためには、システムを理解した上での場の設計・制御が必要不可欠となる。 本シンポジウムでは、材料やデバイスなど場の操作技術を分子生物の研究者と議論することで、新たな実験系を模索することを目指す。
14:20-16:20
- 「次のパンデミック」に備えるための実験ウイルス学の挑戦
Challenges of Experimental Virology to Prepare for the “Next Pandemic”
協賛:国際先導研究 - オーガナイザー
佐藤 佳(東京大学)、福原 崇介(九州大学)詳 細新型コロナウイルスの世界的大流行(パンデミック)から、5年の月日が経った。新型コロナパンデミックは、ウイルス感染症の脅威を白日のもとに晒した。しかし、WHOやCDCが勧告するように、COVID-19は人類史における最後のパンデミックではない。「次のパンデミック」という新たな感染症リスクに備えるためには、分子生物学や細胞生物学を駆使した「実験ウイルス学」は必須である。本シンポジウムでは、「次のパンデミック」に備えるために必要な、分子生物学に基づいたウイルス研究について議論したい。
14:20-16:20
- 不均一性制御の定量生物学2025
Quantitative Biology of Heterogeneity Regulation 2025 - オーガナイザー
中山 淳(大阪国際がんセンター)、宮田 憲一(がん研究会 がん研究所)詳 細近年のオミクス解析や1細胞解析の飛躍的な発展により、組織発生・加齢・がんなど、様々な細胞・遺伝子発現の時空間的な不均一性が明らかになりつつある。本シンポジウムでは、生体内のあらゆる不均一性は単なるばらつきではなく、生命が多様性を維持するための基盤と捉え、これを「定量的」に評価することで、新たな生物学の地平を切り開くことを目指す。不均一性の定量解析、1細胞解析、ライブイメージング、など、幅広い知見から生体内不均一性の制御と動態について議論する。
14:20-16:20
- 変遷する細胞外小胞研究とその未来
Perspective of diverse EV research
協賛:日本細胞外小胞学会 - オーガナイザー
横井 暁(名古屋大学)、山本 雄介(国立がん研究センター研究所)詳 細あらゆる生命現象の中でエクソソームを中心とする細胞外小胞は重要な役割を果たすことが明らかになっており、その驚くべき可能性は今現在もアップデートされ続けている。細胞外小胞・エクソソームを取り巻くマーケットが世界的に拡大の一途をたどる今、その基礎的理解を緻密に進めることの重要性がより高まっている。本セッションでは、多様な学術領域における最先端の知見を集結することで、細胞外小胞研究の魅力と未来を議論する。
14:20-16:20
- 糖尿病の分子生物学:インスリン分泌と抵抗性のメカニズム
Diabetes: Novel insights into mechanisms of impaired insulin secretion and insulin resistance - オーガナイザー
平池 勇雄(東京大学)、宮地 康高(九州大学)詳 細糖尿病は膵β細胞からのインスリン分泌の低下と主に肥満が惹起する骨格筋、肝臓、脂肪組織などインスリン標的臓器におけるインスリン抵抗性の双方によって発症する。本シンポジウムでは国内外から気鋭の若手研究者が集まり、分子生物学的なメカニズム解析と大規模データの網羅的解析や機械学習の活用を両輪として明らかになりつつある糖尿病の新たな分子病態と創薬標的、先制医療の実現へ向けた展望について議論する。
9:00-11:00
- 光・化学操作により捉える細胞増殖メカニズム
Illuminating Cell Proliferation Mechanisms with Light or Chemical Manipulation - オーガナイザー
川島 茂裕(東京大学)、知念 拓実(東京大学)詳 細細胞周期の進行過程では、染色体や微小管、細胞膜の機能や構造、さらにはタンパク質や核酸の修飾状態が迅速かつ動的に変化します。これらのプロセスを人為的に操作することは、細胞の増殖メカニズムの理解を深めるだけでなく、新たな創薬の可能性を開拓する上でも重要です。本セッションでは、「光」や「化学(化合物)」を活用した新しい操作手法を用いて、細胞増殖プロセスを解明する最先端の研究に焦点を当てます。参加者同士で当該分野における革新的なアプローチを共有し、分野を超えた協力を促進するための新たなプラットフォーム形成を目指します。
9:00-11:00
- 遺伝子発現・非遺伝子発現を司るnon-canonical転写制御
Non-canonical transcription regulation of gene expression and non-gene expression - オーガナイザー
高橋 秀尚(横浜市立大学)、二村 圭祐(群馬大学)詳 細遺伝子発現制御においては転写はセントラルドグマの最初のステップとして非常に重要な役割を果たしている。そころが、最近の研究によって、転写は遺伝子発現に加えて、遺伝子発現以外の細胞機能も司ることが明らかとなってきた。本シンポジウムでは、このようなnon canonicalな転写機構を介した新たな細胞機能制御について最新の知見を交えて議論したい。
9:00-11:00
- 攪乱RNA-生体を負に制御するRNAの生理とその適応機構
Perturbing RNAs: Physiology and co-option mechanisms of RNAs disrupting organismal homeostasis - オーガナイザー
河原 行郎(大阪大学)、小林(石原) 美栄(慶應義塾大学)詳 細ウイルス由来の外来性RNA、自己由来にも関わらず免疫を惹起する内因性RNAなど、RNAそのものが生体の恒常性を負に制御する例が明らかになってきた。ではそれらRNAは具体的にどのように生体に悪影響を及ぼすのか?また、生体はそれらをどう認識し対抗し、時に生存に有利になるよう利用しているのか?本シンポジウムでは生命システムを「攪乱する」RNAの知見を情報科学・進化学・免疫学・神経科学など、分野横断的にまとめ、その生理的影響と適応機構について議論する。
9:00-11:00
- オートファジーから拡がる膜界面生物学
Autophagy expanded: decoding membrane interface biology
共催:学術変革領域研究 (A)「オートファジーから拡がる膜界面生物学」 - オーガナイザー
野田 展生(北海道大学)、池ノ内 順一(九州大学)詳 細細胞は水以外では主にタンパク質と脂質でできている。タンパク質集団の機能は相分離研究で注目されてきたが、脂質分子集団との連携は見過ごされてきた。オートファジーでは、タンパク質集団が膜界面で脂質集団とダイナミックに相互作用し、複雑な膜動態を生む。本シンポジウムでは、この“膜界面分子協奏”がオートファジーや一細胞に収まらない多様な生命現象に果たす役割について、最新の知見を紹介するとともに、その普遍的役割を議論したい。
9:00-11:00
- 栄養・代謝から紐解く老化、加齢性疾患
Nutrition and metabolism in aging and age-related diseases - オーガナイザー
近藤 嘉高(東京都健康長寿医療センター)、藤田 泰典(東京都健康長寿医療センター)詳 細健康寿命の延伸における食事の重要性は、これまでに広く認識されてきた。近年の解析技術の進歩により、老化や加齢性疾患に関連する栄養素や代謝物質の新たな役割、意義が明らかにされつつある。本シンポジウムでは、食事の三大栄養素バランス、脂肪酸、アミノ酸、代謝変容、老化促進分子などの観点から、健康増進および老化や加齢性疾患の分子機序解明にアプローチする最新の研究を紹介したい。
9:00-11:00
- バクテリアとオルガネラでの核様体形成と代謝との共役機構の最前線
Coordination between nucleoid structure and metabolism in bacteria and organelles - オーガナイザー
加生 和寿(九州大学)、大島 拓(富山県立大学)詳 細ミトコンドリアや葉緑体は細胞の糖代謝やエネルギー産生に重要なオルガネラである。オルガネラ独自の環状ゲノムは原核生物と同様の非クロマチン型の核様体構造を形成する。近年、この核様体構造が原核生物、オルガネラいずれにおいてもDNA複製、機能発現、恒常性維持などと密接に関連することが分かりつつある。本シンポジウムでは幅広い生物種の核様体研究を結集し、新たな共通原理の解明に挑む。
9:00-11:00
- 染色体の構造と機能を支える超分子複合体
Chromosome structure and function driven by supramolecular complexes
協賛:学術変革領域研究(A), クラスター細胞学 - オーガナイザー
村山 泰斗(国立遺伝学研究所)、高橋 元子(がん研究会 がん研究所)詳 細長大なゲノムDNAは、様々なタンパク質複合体によって複雑な立体構造を形成し、転写、複製、染色体分配など多様な生命活動が制御される。個々の因子の構造や生理活性が深く研究されてきた一方、これらのタンパク質複合体は、より高次の相互作用を介して超分子複合体を形成することで生理的な機能を発揮することが明らかになってきた。本シンポジウムでは、転写から染色体分配までの幅広い分野で活躍する国内外の研究者を招き、超分子複合体が駆動する染色体機能の発現と制御機構について議論する。
9:00-11:00
- 超高齢社会のQOL向上のための地球環境因子と全身と末梢を繋ぐ多細胞生命システム適応基盤
Multicellular Life System Adaptation Platform Linking Global Environmental Factors and the Whole Body and Peripheral Organs for Improving Quality of Life in a Super-Aged Society - オーガナイザー
跡見 順子(帝京大学先端総合研究機構)、清水 美穂(帝京大学先端総合研究機構)詳 細人間も、地球に創発し構成する環境因子(重力・光・酸素等)に対してホメオスタシスを維持するべく適応進化してきた生命体(自然物)であるが、唯一納得する知識で随意的に行動を変えることができる存在である。細胞—身体システムが機能しているホメオスタシス範囲を逸脱する刺激(ストレス)は、炎症を誘導する。本シンポジウムでは、ロコモ・メタボ・癌等の疾病への予防対策として、トータルに免疫系やストレス応答系を適切に作動させ、健康度を向上させる方向性を環境因子を考慮して時空間統合的に探る。
9:00-11:00
- 神経伝達物質受容体の多層的理解と機能制御:原子から個体へ
Multi-level understanding and functional regulation of neurotransmitter receptors: From atoms to living organisms - オーガナイザー
清中 茂樹(名古屋大学)、山下 敦子(大阪大学)詳 細クライオ電顕やAIベースの構造予測の進展により、神経伝達物質受容体分子の原子レベルでの理解は飛躍的に深まった。また、それらの静的な構造情報を動的に理解するための高速AFMなど、ダイナミクス解析手法も大きく進展した。一方で、これら原子レベルの理解に基づき、受容体の機能制御手法、特にケミカルバイオロジー的手法も急速に発展した。本シンポジウムでは受容体の原子レベルの理解が個体レベルの機能制御に結びつく現状と展望を議論する。
9:00-11:00
- ほねほねロック ~さまざまな動物が奏でる多様な骨格形成~
Hone-Hone rock: The diverse skeletogenesis orchestrated by various animals - オーガナイザー
熱田 勇士(九州大学)、黒田 純平(大阪大学)詳 細偏に「骨」といっても、その形状は動物種間で実に多様である。そして、この多様性こそ、動物のかたちや行動様式のバリエーションを生み出す基盤となる。しかしながら、骨格系がどのように形成され、多様性が生み出されるのかについては未だ不明な点が多い。本シンポジウムでは、哺乳類から無脊椎動物に至るまで、さまざまな生物が奏でる“骨格形成のメロディー”に耳を傾け、多彩な骨格系の成り立ちについて、その理解を深めることを目指す。
9:00-11:00
- 多能性幹細胞を用いた研究の最前線
Frontiers in pluripotent stem cell research and applications - オーガナイザー
宮岡 佑一郎(東京都医学総合研究所)、林 洋平(京都大学iPS細胞研究財団)詳 細ヒト多能性幹細胞は、in vivo実験が不可能なヒトの⽣命現象に対して、分⼦・細胞・発⽣⽣物学的研究を行うためのプラットフォームとなり、またその応⽤としての再⽣医療や創薬に貢献している。本シンポジウムは、ヒト多能性幹細胞を⽤いて、リプログラミング、ゲノム編集、パイオニア因⼦、トランスクリプトーム、プロテオーム、病態モデル、治療法開発といった分野の最前線の研究を紹介するとともに、多能性幹細胞研究のさらなる発展を考える契機とする。
9:00-11:00
- 小胞体の機能を支える多彩な分子メカニズム
Diverse molecular mechanisms supporting functions of the endoplasmic reticulum - オーガナイザー
蜷川 暁(神戸大学)、堤 智香(京都産業大学)詳 細全タンパク質の約1/3を生合成する小胞体は、作られたばかりの「未成熟のタンパク質」から、壊すべき「不要なタンパク質」までを扱う。そのため、極めて精密で多彩な分子機構を有しており、世界の研究者が現在も様々なアプローチを試み、新たな発見がなされ続けている。本セッションでは海外演者を含む最先端で研究を行う若手研究者を招集し、小胞体の機能を支える分子機構について多角的な視点から、最新の知見を交えて深く議論する場としたい。
9:00-11:00
- ゲノムエポックが引き起こした大進化を探す
Genomic epoch exploration causing macroevolution - オーガナイザー
遠藤 俊徳(北海道大学)、峯田 克彦(早稲田大学・静岡理工科大学)詳 細生物の大進化はどのようにして起きるのだろうか。このダーウィン以来の大問題は、多くの生物ゲノムが解読された今も未解明のまま取り残されている。ゲノム倍加が見られる生物でもみかけがほとんど変わらない例は多い。むしろ、小規模であっても重大な質的変化こそが、生物の大進化を生み出したのだろう。例えば眼の誕生に関わった遺伝子は多細胞生物の劇的な多様化を導いたとされる。こうした質的変化、ゲノムエポックについて考えたい。
9:00-11:00
- メタボローム研究の最前線
The Frontiers of Metabolome Research - オーガナイザー
平山 明由(慶應義塾大学)、和泉 自泰(九州大学)詳 細”メタボローム”という言葉が広く知られるようになってから20年以上の月日が経過した。その間に、質量分析装置の高感度化をはじめ、測定技術の多様化や高速化など、分析化学を中心とした技術革新が継続的に行われてきた。本セッションでは、最新のメタボローム解析技術と分子生物学領域における応用例を中心に紹介し、今後のメタボローム研究の目指す道について議論する。
9:00-11:00
- 転移因子コードが誘導する核内3次元構造形成メカニズムの理解
Higher order genome regulation and function mediated by the transposable element code - オーガナイザー
一柳 健司(名古屋大学)、藤 泰子(東京科学大学)詳 細SINEやLINEなどの転移因子はゲノムの多くの部分を占める。SINEとLINEはゲノム内に不均一に、しかも相互排他的に分布する。近年、SINEがCTCFなど核内3次元構造を制御する因子をリクルートすることや特定のヒストン修飾を持つヌクレオソームを持つこと、また、LINE RNAが核内での液-液相分離を介してヘテロクロマチンを構築することが示された。本シンポジウムでは、転移因子が結合タンパク質と協奏することで核内3次元構造を制御するという分子コード(転移因子コード:TEC)の概念を提唱し、転移因子や核内3次元構造に関連する幅広い最新の研究から議論したい。
9:00-11:00
- 次世代形質を左右する母胎連関ネットワーク
Bidirectional molecular network in fetal-maternal crosstalk regulating fetal development - オーガナイザー
三原田 賢一(熊本大学)、豊島 文子(東京科学大学)詳 細哺乳類の発生は、胎児自律的な機構に加え、母体-胎児間の分子的なやり取りに大きく依存している。近年、母胎連関の実態が遺伝子、分子、細胞レベルで解析され、発生の早期における母体環境がエピゲノム制御を通じて出生後の子の健康状態にも深く関わっていることが明らかとなりつつある。本シンポジウムでは、母胎連関に関わる双方向ネットワークの分子生物学的メカニズムについて議論する。
9:00-11:00
- 核酸と感染症の病態制御
Nucleic Acids and Pathogenesis of Infectious Diseases - オーガナイザー
高橋 朋子(埼玉大学)、南宮 湖(慶應義塾大学)詳 細人類はパンデミックをはじめとして感染症の脅威にさらされており、その制御は喫緊の課題である。近年の研究により核酸を用いた新たな診断技術や治療法が急速に発展しており、感染症分野への応用が強く期待される。核酸は病原体由来の遺伝情報としての役割にとどまらず、宿主の免疫応答を制御する因子としても重要な機能を担う。本シンポジウムでは、感染症における核酸の役割に焦点をあて、核酸と感染症研究の新たな可能性を議論する場としたい。
9:00-11:00
- 植物細胞可塑性:数瞬の応答から悠久の進化にまで通底する適応機構
Plant cell plasticity from ephemeral to millennial timescales - オーガナイザー
福島 健児(国立遺伝学研究所)、松永 幸大(東京大学)詳 細植物は動物とは異なり、過酷な環境からの逃避行動をとらないため、直面するストレスには各細胞が自らの性質を変化させながら対応しなければならない。この可塑的な性質は、応答・発生・進化といった多角的な側面で、植物という生き方を特徴づける。本シンポジウムでは、この仕組みを分子レベルで解明する研究者が集い、「植物細胞可塑性」について議論を深める。
14:20-16:20
- 新規モデル生物とバイオDX
BioDX for new model organisms
共催:JST COI-NEXT バイオDX産学共創拠点 - オーガナイザー
中前 和恭(広島大学)、坊農 秀雅(広島大学)詳 細非モデル生物とも呼ばれる新規モデル生物のゲノム解析は、生命科学におけるDigital Transformation(バイオDX)の普及、特にビッグデータの利活用によって急速に進みつつある。一方で、バイオDXのノウハウは各分野で十分に共有されているとは言い難い。本シンポジウムでは、新規モデル生物解析を行う研究者同士が情報交換し、既存のモデル生物にとどまらない多彩な分子生物学の発展を目指す。
14:20-16:20
- オープンライフサイエンスの新時代
New Era of Open Life Science - オーガナイザー
大浪 修一(理化学研究所)、粕川 雄也(理化学研究所)詳 細オープンライフサイエンスは、研究データや技術、知識の共有を促進し、研究の透明性を向上させるとともに、科学的発見や社会課題の解決を加速します。近年、生命科学データの大規模化・多様化、知識の精緻化、AIや情報通信技術の進展により、オープンライフサイエンスは新たな時代を迎えています。本シンポジウムでは、日本のオープンライフサイエンスを牽引する各機関の最新戦略を共有し、科学的・社会的成果の創出に向けた戦略を成功例を示しながら議論します。
14:20-16:20
- 膜・非膜オルガネラとコンタクト:動態と機能の新視点
Membrane and Membraneless Organelles and Their Contacts: New Perspectives on Dynamics and Function
共催:生命創成探究センター - オーガナイザー
椎名 伸之(自然科学研究機構)、中津 史(新潟大学)詳 細近年、液-液相分離による非膜オルガネラの形成や、異種オルガネラ間のコンタクト構造が細胞機能の制御に果たす重要な役割が明らかになりつつある。これらの構造は環境変化に応じて動的に変化し、オルガネラや細胞機能を精緻に調整する仕組みを備えている。本シンポジウムでは、これらの構造の動態や分子メカニズムに関する最前線の研究成果を紹介し、それらが細胞機能にどのように寄与するのかを議論する。さらに、先端技術を駆使した研究が、新たな細胞機能制御メカニズムの解明に与えるインパクトについても展望する。
14:20-16:20
- 遺伝子発現と染色体制御の多様性
Gene Expression and Chromosomal Regulation Diversity across Model Organisms, and in Tissue- and Developmental Stage-Specific Contexts - オーガナイザー
澁谷 大輝(理化学研究所)、深谷 雄志(東京大学)詳 細生命現象の本質を理解するためには、特定の生物種や均一な細胞集団を用いたシンプルなモデル研究だけでは不十分である。動物から植物に至る多様なモデル生物(さらには非モデル生物)を解析し、同一のモデル生物においても異なる発生段階や臓器種における比較を行うことによって、生物種・発生段階・臓器種に特異的な制御や、あるいは逆に機能的収斂や強固に保存された制御が見えてくる。本シンポジウムでは、遺伝子発現や染色体制御の観点から、動物と植物、体細胞と生殖細胞など、さまざまなモデル研究を紹介し、今後の生物学研究の展望について議論を深める。
14:20-16:20
- 全能性細胞における細胞運命制御機構
Mechanisms of Cell Fate Control in Totipotent Cells - オーガナイザー
石津 大嗣(慶應義塾大学)、原田 哲仁(九州大学)詳 細受精卵が配偶子の受精を通じて全能性を確立し、その後の運命制御によって多様な発生過程へ進む仕組みには多くの未解明な点が残されている。その鍵を握るのは、全能性や多能性の獲得に関わる遺伝子機能とエピジェネティクス制御である。本シンポジウムでは、これら分子基盤の最新知見を共有し、さらに合成生物学的アプローチによる試験管内発生再現など、新技術がもたらす全能性運命制御の新展開を紹介する。
14:20-16:20
- 腎臓と血圧の多様な働きと病態を最先端の研究から理解する
Understanding the Diverse Functions and Pathophysiology of the Kidney and Blood Pressure Through Cutting-Edge Research
共催:日本腎臓学会 - オーガナイザー
豊原 敬文(東北大学)、小豆島 健護(横浜市立大学)詳 細腎臓は150g程度の臓器だが、重量当たりの血流量は体内で最も豊富であり、老廃物の排泄のみならず液性調節による血圧制御や内分泌機能など多様な働きを有する。また腎疾患の病態も流体刺激、高血圧、炎症などが関わり複雑であるが、一細胞オミクスや患者由来iPS細胞などによって腎臓再生・移植、またメカノバイオロジーや液性制御研究によって高血圧の基礎的理解が進んでいる。本シンポジウムでは腎臓と血圧の多様な働きや病態の最新知見について共有する。
14:20-16:20
- スプライシング:その精巧なメカニズムと破綻による疾患
RNA splicing : its sophisticated mechanism and diseases caused by disruption - オーガナイザー
片岡 直行(東京大学)、甲斐田 大輔(富山大学)詳 細高等真核生物の核ゲノムにコードされる遺伝子のほとんどは、イントロンと呼ばれる介在配列によって分断化されている。そこでmRNA前駆体からイントロンを除き、エクソンを連結するスプライシングは遺伝子発現過程の中心となっている。スプライシングは精巧な過程であり、その機構解明が進んでいる一方、その制御に破綻をきたした場合、疾患として現れる場合も多く報告されている。本シンポジウムでは、スプライシングの機構とその破綻による疾患に焦点を当て、最新の知見を紹介する。
14:20-16:20
- エピゲノム制御が司る生命現象とその破綻による疾患発生
Epigenetic regulation controls development and disease onset - オーガナイザー
竹島 秀幸(星薬科大学)、竹信 尚典(埼玉県立がんセンター)詳 細エピゲノムによる制御は我々の体の形成に必要不可欠であり、様々な生命現象に重要な役割を果たす。一方で、我々のエピゲノムは様々な外部要因によって異常に書き換えられ、その異常が蓄積することで、がんなどの疾患の発症につながる。本シンポジウムでは、エピゲノムとその制御因子に焦点をあて、それらがどのような分子メカニズムで組織の発生から疾患発症につながるのかを紹介する。
14:20-16:20
- アシル化の生物学
Biology of Acylation - オーガナイザー
梅原 崇史(立命館大学)、古園 さおり(東京大学)詳 細近年、高感度な質量分析により、タンパク質のリジンやシステイン残基に代謝産物由来の長鎖・短鎖の様々なアシル化修飾が発見されつつある。これらのアシル化修飾は環境応答や細胞機能の制御に関連していることが示唆されつつあるが、生化学的にも細胞生物学的にも未開拓な分野である。そこで、タンパク質のアシル化修飾に関する最新の話題を様々な観点から紹介し、今、アシル化研究の何が面白くて何がボトルネックかを議論する。
14:20-16:20
- 植物の運動:目立たないが重要な運動のメカニズムを探る
Plants in Motion: Exploring the mechanisms behind their subtle yet vital movements - オーガナイザー
森田(寺尾) 美代(基礎生物学研究所)、郷 達明(奈良先端科学技術大学院大学)詳 細植物は、人間の目には捉えにくいものの、成長や環境応答の過程で絶えず動き続けている。植物の運動は、タイムスケール、駆動機構、直面する力のダイナミックレンジにおいて、動物とは本質的に異なる。本シンポジウムでは、植物の普遍的な運動の基盤メカニズムを、生理学、分子遺伝学、細胞生物学、物理・工学、進化の各視点から最前線の研究者が紹介する。分野横断的な議論を通じ、新たな展望を切り開く。
14:20-16:20
- 「延長された表現型」の分子メカニズム:異種生物同士の相互作用を支えるエフェクター研究の最前線
The Molecular Mechanisms of the Extended Phenotype: The Cutting Edge of Effector Research Supporting Interactions Between Heterospecific Organisms
共催:学術変革領域研究(A)「共進化表現型創発:延長された表現型の分子機構解明」 - オーガナイザー
丹羽 隆介(筑波大学)、春本 敏之(産業技術総合研究所)詳 細自然界では、ある生物の遺伝情報が、他種の生物の表現型として発現していると解釈される現象が、特に寄生や内部共生といった近接的な生物間相互作用において普遍的にみられる。このような現象は、Dawkins (1982) によって提唱された「延長された表現型」の典型例である。しかし、その具体的な分子メカニズムについてはほとんど理解が進んでいない。本シンポジウムは、「延長された表現型」の分子機構に関する様々な生物を用いた研究の最前線を紹介することを目的とする。
14:20-16:20
- 染色体配列解読の革新がもたらすゲノム科学の未来像
Chromosome-level genome assemblies: Transforming the future of genomics - オーガナイザー
今 鉄男(University of Vienna)、濱田 麻友子(岡山大学)詳 細近年、ロングリードとHi-C解析から染色体配列を構築する手法が確立し、研究室単位で研究対象種の染色体配列が解読可能となった。以前は染色体レベルの解析はモデル生物に限られていたが、ここ数年で幅広い生物種の染色体配列が解明され、遺伝子機能と染色体スケールの情報を統合した“グローカル(glocal)”な視点で、生命科学が展開されている。本シンポジウムでは、哺乳類から無脊椎動物、植物までユニークな特徴を持つ生物種を用い、染色体配列解読を駆使して新たな生物学を切り拓く国内外の若手研究者を招き、研究事例をもとに、ビッグサイエンスから個別研究へと転換しつつあるゲノム科学の現状と未来像について議論を深める。
14:20-16:20
- 多元的アプローチから迫る心臓システムの理解
Exploring the fundamental mechanisms of the cardiac system through multidisciplinary research - オーガナイザー
松花 (谷) 沙織(神戸大学)、福井 一(徳島大学)詳 細私たちの生命を支える心臓はどのように形づくられるのか?これまでの心臓研究から、多様な細胞による発生のしくみが見えてきた。心臓の成り立ちの全容を理解するためには、細胞や組織情報の包括的な解析や、細胞による自律的・他律的原理の探求など、多元的な研究が欠かせない。本シンポジウムでは、空間トランスクリプトーム、生体イメージングや数理モデル解析などを駆使した最新の知見を紹介し、心臓・循環器システムの発生と機能のさらなる理解にむけて、分野横断的に議論する場としたい。
14:20-16:20
- ここまで来た腎臓オルガノイド研究 ~腎臓再生への道~
State of the Art Kidney Organoid Research to Rebuild a Transplantable Kidney
共催:国際先導研究(西中村代表)「腎臓を創る」 - オーガナイザー
高里 実(理化学研究所)、横川 隆司(京都大学)詳 細世界人口の約10%が慢性腎臓病を患っているとされており、200万人以上が人工透析や腎移植を受けている 。その一方で、根治的治療法は存在せず腎移植のドナーも圧倒的に不足している。複雑な構造と機能を有 する腎臓を人工的に作るということは夢物語とされていたが、2014年に腎臓オルガノイド作製が成功したことで、流れが一変した。この10年で腎臓オルガノイドは遺伝性腎疾患 の病態再現に用いられつつある。しかし現行のヒトオルガノイドは腎臓という臓器に特有の全体構造をまだ有しておらず、機能的にも未熟である。本シンポジウムでは、将来の移植医療のために、高次な構造と機能、成熟度を持つ次世代腎臓オルガノイドの作製を目指した最先端研究を紹介する。
14:20-16:20
- ミトコンドリアで働く分子たち -その振る舞いを基礎から見つめ直す-
Molecules in Mitochondria -Rethinking of their functions from basics- - オーガナイザー
荒磯 裕平(金沢大学)、吉井 紗織(東京大学)詳 細近年、ミトコンドリアに関する新規機能が次々と解明され、細胞の恒常性維持機構の根幹を担うミトコンドリア研究は目覚ましい進歩を遂げている。本シンポジウムでは、これらの機能を支えるタンパク質やRNA、低分子化合物に着目し、ユニークな研究を展開する若手研究者を中心に最新の知見をご紹介いただく。ミトコンドリアで働く分子たちの機能、構造、制御技術を、様々な視点から議論することで、ミトコンドリア生物学の根幹に迫り、新しいミトコンドリア像を見出す。
14:20-16:20
- RNAと結合タンパク質が支配する超複雑系の作用原理の解析
Analysis of working principle of a super complex system governed by RNA and its binding proteins - オーガナイザー
黒川 理樹(埼玉医科大学)、片平 正人(京都大学)詳 細相分離に関与するRNA結合タンパク質(RBP) FUS/TLSは、数千種類のRNAと結合する。TLSは、さらに、複数のRBPと複合体を形成することから莫大な数のRNA分子とタンパク質複合体が形成される。RNAとRBPの結合には、非特異性と特異性が混在しており、偶然と必然により精緻に制御されている。この複雑系を支配する分子原理の解明に果敢に挑戦する研究者の会を企画する。ここでの個性的な論議を期待する。
14:20-16:20
- 老化と神経機能における糖と脂質代謝制御の分子機構
Molecular mechanisms regulating carbon and lipid metabolism in aging and neuronal function. - オーガナイザー
稲田 利文(東京大学)、魏 范研(東北大学)詳 細遺伝と代謝は生命の基盤であり、分子レベルでの相互寛解の理解が急速に進んでいる。遺伝子発現の正確性は生命現象の基盤であり、その恒常性の破綻は疾患の原因となる。多様な品質管理機構による遺伝子発現の正確性を保証する分子機構の理解が急速に進んでおり、代謝機能も解析が進んでいる。本シンポジウムでは老化と神経機能における糖と脂質代謝制御の分子機構に関する最近の進展について紹介する。
14:20-16:20
- 核膜関連研究の新展開:多様な生物学的機能と疾患との関連
New frontier in nuclear envelop: cellular and pathological functions - オーガナイザー
上野 勝(広島大学)、正井 久雄(東京都医学総合研究所)詳 細核膜は、遺伝情報の複製と安定な維持、損傷修復、発現制御やこれらを担う染色体高次構造形成などにおいて重要な役割を果たす。特に、核膜の異常は早老症などの遺伝病やがんと密接に関係する。最近、機械的ストレスによって損傷した核膜が、修復機構によって修復されることがわかってきた。本シンポジウムでは、複数の若手研究者の演題を公募し、タンパク質・脂質の相互作用を介した核膜形成・修復制御と、その異常が細胞・染色体機能や疾患発生に及ぼす影響に関する最新の研究成果と今後の展開について幅広く議論する。
ミニシンポジウム テーマ一覧
※公募企画 と記載のあるシンポジウムでは、一般演題から演題を採択予定です。
※セッション番号について:
開催日 + ミニ(M) + シンポジウム(S)+ -(ハイフン)+ 会場
(例)3MS-05:第3日目・ミニ・第05会場
※時間について:各日11:15-12:35
※講演言語について:
E 英語 J 日本語
11:15-12:35
- エボロジー~オルガネラヒモロジーから紐解く生物進化~
Evolution + Organelle superstring theory = Evology - オーガナイザー
安藝 翔(東京大学)、椎葉 一心(学習院大学) -
詳 細
真核細胞のオルガネラは、動的な形態変化や物質輸送を通じてネットワークを形成し、生体恒常性やシグナル伝達を制御する。このネットワーク、「オルガネラヒモロジー」は、生物進化で普遍性と多様性を獲得し、細胞機能の高度化に寄与してきた。本シンポジウムでは、超解像度顕微鏡やオミクス解析を活用した最新研究や多様なモデル生物で得られた知見を共有し、新たな研究分野の創生と共同研究の促進を目指す。
11:15-12:35
- 心臓生物学の新展開
Emerging cardiac biology - オーガナイザー
真鍋 一郎(千葉大学)、尾池 雄一(熊本大学) -
詳 細
現在の心臓研究は、従来の心臓・心筋細胞セントリックな視点を超え、心臓を構成する多様な細胞社会や、代謝、免疫、神経系等との緊密な相互作用ネットワークの解明へと大きく展開している。この最先端の研究アプローチがもたらす発見は、心臓研究の枠を超えて生命科学全体に新たな視座を提供している。本シンポジウムでは、心臓研究に馴染みのない会員にも最新の研究潮流を広く紹介し、異分野の研究者との対話を通じて次世代の生命科学研究の創出を目指したい。
11:15-12:35
- 分子修飾が生み出す生命の制御と疾患
Molecular Modification Produces Regulation of Biological Functions and Diseases - オーガナイザー
今野 雅允(産業技術総合研究所)、常陸 圭介(藤田医科大学) -
詳 細
DNA、RNA、タンパク質など、さまざまな生体分子は修飾を受けることでその機能が制御され、複雑な生命現象、さらには疾患の発症、悪性化に寄与する。本シンポジウムでは、若手研究者による分子修飾に関連した最先端の研究成果を紹介することで、生命における分子修飾の重要性の理解を深め、この分野への新規参入のきっかけを提供する。
11:15-12:35
- スキマの分子生物学
Molecular Biology of The Gap - オーガナイザー
村井 純子(愛媛大学)、中田 聡(群馬大学) -
詳 細
生物は様々な場面においてスキマ(ギャップ)を認識し、それを秩序に基づいて修復・充填する能力を備えている。例えば、DNA複製時のギャップや、除去された細胞間のスキマを埋める組織リモデリングである。一方で認識されないスキマもある。本シンポジウムでは、分子・細胞・組織の各階層に共通して保存されているスキマ認識や補填にフォーカスした’スキマ生物学’を立ち上げて、生物学的意義について議論を深めたい。
11:15-12:35
- 何が私たちを形作るのか?遺伝子、身体、文化による人類進化の多階層的理解
What shapes us human? Understanding human evolution through genes, bodies, and culture - オーガナイザー
野村 真(京都工芸繊維大学)、松前 ひろみ(東海大学) -
詳 細
ホモ・サピエンスが備える独自の遺伝的、解剖学的、文化的特徴はどのように進化してきたのか?世界規模でヒトゲノム解読が進み、人類進化の理解は転換期を迎えている。そこで本シンポジウムでは、遺伝子、身体の発生や機能、身体から創出される文化(言語)など、さまざまな階層からヒトの進化を検証する。国内外のゲノム生物学者、解剖学者、発生学者らによる講演から「ヒトとは何か?」という普遍的な問いへの議論を深める。
11:15-12:35
- 次世代ハイポキシア研究者が巻き起こす生命科学の新潮流
Current Research Trends in the Brand-New Forum for Hypoxia Biology
共催:ハイポキシア研究会 - オーガナイザー
鈴木 教郎(東北大学)、中山 恒(旭川医科大学) -
詳 細
2025年、「がんとハイポキシア研究会」と「低酸素研究会」が融合し、「ハイポキシア研究会」が発足した。2つの旧研究会では、低酸素応答のセントラルドグマ”PHD-HIF経路”を中心とした研究の議論が展開され、国内の研究フォーラムとして一定の成果を得た。一方、PHD-HIF経路が関与しない低酸素応答機構の発見や低酸素状態をストレスではなく細胞運命決定に必要なシグナルとして捉える視点が生まれた。そこで、次世代のハイポキシア研究者が取り組んでいる研究の最前線を紹介する。
11:15-12:35
- 地球と生命の共進化の理解から宇宙生命探査へ
From the Coevolution of Life and Earth to the Search for Life in the Universe
協賛:学術変革B 復元細胞機能学 - オーガナイザー
松尾 太郎(名古屋大学)、渡辺 智(東京農業大学) -
詳 細
地球上の生命は約40億年前の誕生以来、地球表層環境との相互作用を通じて進化を遂げてきた。特に、光合成生物の出現によって地球表層が酸化され、酸素を利用する真核生物や多細胞生物の誕生が促進された。こうした地球での生命進化を理解することは、宇宙における生命探査の可能性を広げる上でも大きな手がかりとなり得る。本シンポジウムでは、進化生物学や地球惑星科学の分野で活躍する研究者を招き、地球と生命の共進化に関する最先端の知見と、それを踏まえた地球外生命探査の展望について議論を深める。
11:15-12:35
- 神経疾患の鍵を握るプロテオスタシス:ユビキチン化とタンパク質分解の新たな視点
Proteostasis as a Key to Neurological disorders: A New Perspective on Ubiquitination and Protein Degradation - オーガナイザー
松本 弦(大阪公立大学)、若月 修二(国立精神・神経医療研究センター) -
詳 細
多くの神経変性疾患や精神疾患では、神経細胞のプロテオスタシス異常が原因として重要視される。プロテオスタシス維持にはユビキチン鎖を介したタンパク質分解系が大きな役割を果たし、異常タンパク質の排除やシグナル伝達調節を担う。そのため、この系の乱れは細胞機能の変容と疾患発症を引き起こす。本シンポジウムでは、神経細胞のプロテオスタシス異常に焦点を当て、ユビキチン化とタンパク質分解によるシグナル伝達変容や凝集体形成の観点から議論する。
11:15-12:35
- 数理データ科学が拓く生命医科学研究の未来
Future of mathematical data science driven biomedical research - オーガナイザー
石川 俊平(東京大学)、織田 遥向(東京大学) -
詳 細
高次元ゲノミクスや多彩なイメージングなど、バイオインフォマティクス技術の進歩によりデータは急速に多様化している。この複雑なデータを有効活用するためには数理データ科学が不可欠である。そこで本国際シンポジウムでは、AI、機械学習、トポロジカルデータ解析、高次元統計など、生命医科学研究に有効な最先端の技術を実例と共に紹介する。ツールを軸に広い視点で、参加者一人一人が自身のデータ解析に有意義な技術に巡り合うことのできるセッションを目指す。
11:15-12:35
- 物理的微小環境による遺伝子発現制御と発生、疾患の理解
Understanding gene expression regulation, development, and disease by the physical microenvironment - オーガナイザー
川合 智子(岡山大学)、劉 孟佳(熊本大学) -
詳 細
従来、遺伝子発現制御はシグナル伝達と転写因子により説明されてきた。しかし、近年、ゲノムの物理的な切断や構造変化、細胞が受ける圧力などの「力」による遺伝子発現制御が器官の形成や機能に必須であること、またその破綻が老化やがんなどの病気を引き起こすことが明らかになりつつある。本シンポジウムでは、ゲノム、細胞、臓器レベルで「力」の専門家をお招きし、力の種類や程度、頻度を遺伝子制御情報として理解することで、体の形成メカニズムや疾患、医療展開を議論する。
11:15-12:35
- 魚類糖鎖生物学-魚類における糖鎖の生理機能に迫る-
Fish Glycobiology-Exploring the Physiological Functions of Glycans in Fish- - オーガナイザー
本田 晃伸(理化学研究所)、田角 聡志(鹿児島大学) -
詳 細
糖鎖の基本的な生合成および代謝機構、さらにはその生理機能については、主に哺乳類動物で解析が進んでいるものの、それ以外の生物、特に生物種特異的な機構についてはほとんど解明されていない。本シンポジウムでは、魚類の糖鎖研究に取り組む研究者が、魚類に特徴的な糖鎖構造や代謝機構、生理機能いついて発表する。これを通じて、魚類糖鎖生物学の発展可能性について活発な議論を行いたい。
11:15-12:35
- 染色体核型解析と大規模ゲノム解析の融合科学
Integrated chromosome biology from karyotypes to whole genome analysis
共催:一般財団法人 染色体学会 - オーガナイザー
田辺 秀之(総合研究大学院大学)、宇野 好宣(東京大学) -
詳 細
染色体の数や形態、すなわち核型は生物種ごとにユニークなゲノムの鳥瞰図であり、核型解析からFISH法、クロマチン解析法、Hi-C法などへ展開を遂げてきた。一方、大規模ゲノム研究はNGS技術の進展に伴い、ロングリード手法に基づいたほぼ完全なDNA配列解読が可能となり、セントロメアやテロメアの詳細な構造も明らかにされてきた。本ミニシンポジウムでは、様々な動物および植物における染色体レベルから大規模ゲノム解析を手掛ける研究を紹介いただき、核型解析の重要性を再認識するとともにゲノム解析と合わせた融合科学としての未来へ向けた発展可能性を論じる機会としたい。
11:15-12:35
- ゲノムアラインメントで生命の樹全体の進化を解明
Genome Alignments: Are We Ready to Unravel Evolution Acrossthe Tree of Life? - オーガナイザー
プレシ シャルル(沖縄科学技術大学院大学)、フリス マーティン(東京大学) -
詳 細
染色体スケールの完全なゲノムアセンブリが、生命の樹全体にわたる生物に対して利用可能になりつつあります。ゲノムアライメントは、数千年から数十億年にわたる進化的スケールを対象とした研究を可能にします。本シンポジウムでは、ゲノムアライメントから得られた最新の生物学的洞察に加え、新しい手法、ソフトウェア、パイプラインについて発表します。
11:15-12:35
- 生命の限定合理性を紐解く:細胞・組織・個体の知的適応
Unraveling the Bounded Rationality of Life: Intelligent Adaptation at Cellular, Tissue, and Individual Levels - オーガナイザー
木村 暁(国立遺伝学研究所)、小坂田 文隆(名古屋大学) -
詳 細
生命体は、時々刻々と変化するあいまいな環境を一部しか観測できないにも関わらず柔軟に適応する能力を備えている。このような「限定合理性」は、AIにはない生命特有の知性と言える。本シンポジウムは、生命の「環境を認識・推論する能力」と「柔軟な振る舞い」に注目することで、「限定合理性」を明らかにする試みを紹介する。細胞・組織・個体レベルでの「限定合理性」を実験的アプローチと理論的アプローチから探求することで、生命の知性に迫る議論を展開したい。
11:15-12:35
- 加齢による生体変容の分子・細胞レベルでの理解
The molecular and cellular mechanisms of aging
共催:JSTさきがけ「加齢による生体変容の基盤的な理解」 - オーガナイザー
渡部 聡朗(国立成育医療研究センター研究所)、三好 知一郎(理化学研究所) -
詳 細
老化を引き起こす根本的なメカニズムはどのようなものだろうか?DNAの変異、遺伝子発現変化、ミトコンドリア代謝、細胞・タンパク質の変性などがその根底にあると考えられるが、その全容は不明である。また、エピジェネティク・クロックやSASP因子等も老化制御に関わることが示唆されている。本シンポジウムでは、老化の本質に迫るためのメカニズム研究や技術開発を進める研究者が最新の研究成果を発表し討論を行う。
11:15-12:35
- 自閉スペクトラム症の異分野横断的理解
Interdisciplinary Understanding of Autism Spectrum Disorders
協賛:日本医療研究開発機構 脳神経科学統合プログラム - オーガナイザー
岩見 真吾(名古屋大学)、小池 進介(東京大学) -
詳 細
自閉スペクトラム症をはじめとした多くの精神疾患は、そのスペクトラム性や疾患間の境界の曖昧さ、診断の難しさ、さらに「精神」を直接観察できないという特性から、理解と治療に多くの課題を抱えています。本シンポジウムでは、精神疾患研究における異分野融合の重要性に焦点を当て、最新技術やデータ解析を活用した新しいアプローチを模索します。免疫学、細胞生物学、データ科学、ヒト―マーモセット脳画像解析など、幅広い分野の専門家が集い、スペクトラム性や精神疾患横断という概念そのものの理解を共有し、各分野での自閉スペクトラム症研究成果についてお互いの理解を深め、診断精度の向上と治療・支援法の開発を目指す議論を展開します。異分野連携による精神疾患研究の未来をともに展望します。
11:15-12:35
- 脂質動態から探る核膜と核膜孔機能の最前線
Advances in Nuclear Membrane and Pore Functions: Exploring Lipid Dynamics - オーガナイザー
松村 美紀(愛媛県立医療技術大学)、Richard Wong(金沢大学) -
詳 細
核膜の脂質動態は、核膜の柔軟性や構造・機能の維持に重要な要素である。本シンポジウムでは、脂質動態と核膜機能に関する最先端の研究を紹介し、学際的な連携を促進するとともに、新たな研究の方向性を探る。また、筋ジストロフィーやリポジストロフィーなど、核膜異常に関連する疾患の理解を深め、脂質代謝研究における核膜の重要性を再認識し、新たな視点や革新的なアプローチを提供する。
11:15-12:35
- 新規アプローチによる運動器理解の深化
High resolution understanding of musculoskeletal system through new approaches - オーガナイザー
吉本 由紀(東京科学大学)、乾 雅史(明治大学) -
詳 細
運動器は精緻な複合器官であり、その理解には骨格筋・腱・骨軟骨の個々のユニットに加え、組織間の相互作用の考慮も重要である。近年scRNAseq解析、組織透明化、オルガノイド等の新規手法から運動器研究に新たな視点が提供されている。本シンポジウムでは新しいアプローチで運動器の形態形成・機能維持・疾病に取り組む研究を取り上げ、その理解の深化を目指す。
11:15-12:35
- ゲノム医療とゲノム代謝・応答・修復
Genome Medicine and Genome Metabolism, Response, and Repair - オーガナイザー
中田 慎一郎(京都府立医科大学)、中沢 由華(名古屋大学) -
詳 細
多くの遺伝性疾患は予後が極めて不良であり、診断から治療開始までの猶予期間が限られている。近年、ゲノム診断技術の進展に加え、遺伝子治療や核酸医療などの新たな治療法が、希少難治性疾患に対する革新的な治療戦略として期待されている。また、基礎医学や生物学における新たな発見が、こうした発展をさらに加速させている。本シンポジウムでは、難治性遺伝性疾患の診断・治療に資する最新の研究成果を、多角的な視点からご紹介する。
11:15-12:35
- 細胞間相互作用が駆動する多細胞ダイナミクス
Multicellular Dynamics Driven by Cell-Cell Interactions - オーガナイザー
菊池 浩二(熊本大学)、三井 優輔(京都大学) -
詳 細
多様な組織構造は、組織ごとに異なる発生プログラムに従った細胞の形態変化や運動、機能分化などの多細胞のダイナミクスにより生み出される。こうした多細胞ダイナミクスは、細胞同士が生化学的/力学的シグナルによって影響し合うことで駆動する。しかし、その分子メカニズムやその破綻により生じる病態の詳細は不明な点が多い。本シンポジウムでは、多細胞ダイナミクスの分子基盤やその破綻による病態などについて、最新の研究成果を紹介する。
11:15-12:35
- 学際融合で挑む代謝・栄養学の新機軸
A New Paradigm in Metabolism and Nutrition through Interdisciplinary Integration - オーガナイザー
宮本 崇史(筑波大学)、高橋 伸一郎(東京大学) -
詳 細
生命科学の深化により、栄養素の多面的な機能とその生理的意義が次々と明らかになってきた。しかし、代謝・栄養学が対象とする栄養素は、生体内で極めて複雑なネットワークを形成しており、その情報伝達システムについては未だ完全には解明されていない。本シンポジウムでは、代謝・栄養学を軸に、分子生物学、システムバイオロジー、数理科学など異分野の研究者が一堂に会し、生命システムにおける栄養素の統合的理解に向けた議論を行う。
11:15-12:35
- 細胞内ナノスケール空間が司る生命現象
Intracellular Nanoscale Spaces as Regulators of Cellular Processes - オーガナイザー
岩間 亮(東京大学)、吉村 柾彦(京都大学) -
詳 細
様々な生体分子が密集する細胞内において、ナノスケールレベルの局所空間は至るところに存在する。これらナノスケール空間での生体分子はマクロ・マイクロスケールとは異なる動態を示すと考えられ、様々な局所空間での生体分子の特異的なふるまいが生命現象の根幹を支えている。本シンポジウムでは、ナノスケール空間における生体分子の挙動および機能の解明や細胞内のナノスケールレベルでの制御を目指す若手研究者の講演を中心に、ナノスケール空間から見た細胞像を議論する。
11:15-12:35
- Vasohibin/脱チロシン化研究の最前線
Advances in Vasohibin and Detyrosination Research
共催:Vasohibin研究会 - オーガナイザー
小林 美穂(東京科学大学)、古谷 裕(東京慈恵会医科大学) -
詳 細
Vasohibin(VASH)ファミリーはα-チューブリンの翻訳後修飾である脱チロシン化を誘導する酵素(TCP)であり、別のTCPであるMATCAP1と併せて世界中で盛んに研究が進められている。これらTCPはそれぞれ発現細胞や機能が異なるが、その生理的役割を十分に考慮していない研究も少なくない。このセッションではVASHの本質的役割の解明を目指す研究者が集まり、日本で始まったVASH研究の最新の知見を紹介しつつ議論する。
11:15-12:35
- 加齢に伴う器官変容のメカニズム
Mechanisms of age-related organ alteration
共催:JSTさきがけ「加齢による生体変容の基盤的な理解」 - オーガナイザー
大東 いずみ(徳島大学)、堅田 明子(九州大学) -
詳 細
世界的に高齢化が深刻な社会問題となる中、近年、我が国においても老化研究が精力的に推進されている。個体老化においては、組織間の相互作用は重要な視点であり、多様な組織・器官における加齢変容の基礎的知見を蓄積し、活用することが肝要である。本シンポジウムでは、JSTさきがけ「加齢による生体変容の基盤的な理解」2022年度採択者の中から、心臓、皮膚、筋肉、胸腺、脳脈絡叢、睡眠における加齢変容の研究者が集まり、最新の研究成果を紹介する。
11:15-12:35
- 未来を創る遺伝子改変技術:発生工学の新たな地平線
Shaping the Future with Gene Editing Technologies: New Horizons in Developmental Engineering - オーガナイザー
山本 正道(国立循環器病研究センター)、畑田 出穂(群馬大学) -
詳 細
モデルマウスは生命現象の解明や病態研究に欠かせないツールであり、近年、遺伝子編集技術、ヒト人工染色体をはじめ様々な革新技術が導入され、飛躍的な進展を遂げている。本シンポジウムでは、時空間的遺伝子操作、染色体レベルでのヒト化、レポーターを用いた1細胞レベルでのリアルタイム観察など、最先端の技術を駆使して見えてきた新たな知見を提供し、参加者とともに最前線の研究成果を深く議論する。
11:15-12:35
- モビローム研究最前線:動く遺伝子の謎に迫る
Frontiers of Mobilome Research: The Secrets of Mobile Genetic Elements
後援:大隅基礎科学創成財団 - オーガナイザー
鈴木 仁人(国立感染症研究所)、新谷 政己(静岡大学) -
詳 細
塩基配列解読・解析技術の革新により、メタゲノムから個々の微生物の染色体ゲノムを高精度に再構築可能になった。一方で、進化や適応の鍵を握る可動性遺伝因子(モビローム)は、多様性の高さや解析の難しさから研究が遅れていた。近年のバイオインフォマティクスや構造生物学の進展により、新奇モビロームの検出や、その動態に重要な因子の発見が可能になりつつある。本シンポジウムでは、最新の研究成果を共有し、その意義と今後の課題を議論する。
11:15-12:35
- リボソームクラブ:リボソーム・翻訳研究の最前線
Ribosome Club: Frontiers in the study of ribosomes and translation - オーガナイザー
北村 大樹(大阪大学) -
詳 細
細胞内でのタンパク質合成を担うリボソームは、すべての細胞で構成が同じである受動的な翻訳装置でしかないと長らく考えられてきた。しかし近年の研究によって、リボソーム不均一性や数多のextra-ribosomal functionが発見され、個体の発生や恒常性維持におけるその重要性が注目を集めている。本シンポジウムでは、これらを含む、リボソームや翻訳に焦点を当てた研究を行っている気鋭の若手研究者を招き、今後のさらなる研究展開について議論したい。
11:15-12:35
- 生命維持の要:多様な生物における膜輸送体の機能と進化
Essentials of Life: function and evolution of transporters across diverse organisms - オーガナイザー
永嶌 鮎美(東京科学大学)、小林 彰子(東京大学) -
詳 細
生物は環境認識と適切な応答により生存を維持し、その過程で膜輸送体は、情報受容と恒常性維持の両面で多様な機能を発揮する。膜輸送体はオーソログ間でその輸送特性が必ずしも同一ではなく、その作用機序を理解するには、分野横断的に多角的な視点の研究が求められる。本シンポジウムでは、多岐にわたる生物の膜輸送体における、イオン・水・食品成分といった多様な基質の輸送特性や進化的変化について、様々な手法を用いた膜輸送体研究の最先端を独自の視点から議論したい。
11:15-12:35
- タンパク質複合体の動的相互作用と機能解明
Dynamic Interactions and Functional Analysis of Protein Complexes - オーガナイザー
高橋 将晃(アブドラ王立科学技術大学) -
詳 細
本シンポジウムでは、タンパク質複合体の動的相互作用が生体内での機能発現にどのように寄与しているかを、多角的な手法を用いて解明する最新の研究を紹介します。特に、一分子蛍光イメージング、質量分析、NMR、クライオ電子顕微鏡(cryo-EM)などの先進的な技術を活用した研究に焦点を当て、DNA複製、転写、シグナル伝達など、さまざまな生物学的プロセスにおけるタンパク質複合体の機能とその制御メカニズムについて議論します。さらに、深層学習技術を用いたデータ解析や分子動力学シミュレーションなど、最新の計算科学的手法を組み合わせたアプローチも取り上げます。
11:15-12:35
- 神経系の修復と保護への新たなアプローチ
New approaches to nervous system repair and protection - オーガナイザー
鯉沼 真吾(東京理科大学)、村田 等(岡山大学学術研究院医歯薬学域) -
詳 細
発生期の神経ネットワーク形成の解明は、20世紀最後の20年間における生物学の金字塔の一つである。そして神経系の始めから終りまでを、多様な面を持つ「1つのロジック」として語れるかどうかが、現在の課題として現れている。このロジックは、ヒト成体神経系の修復と保護を目指す指導原理になると期待される。本企画は、代謝、グリアとニューロン、細胞骨格と膜の制御、エピジェネティクスなど多様な分野の知見を持ち寄り、そのロジックを議論する場を目指す。
11:15-12:35
- 雷!プラズマ駆動型科学にみる植物内分子応答
Inazuma! Molecular Responses in Plants Mediated by Plasma-Driven Sciences
協賛:学術領域変革研究(A)「プラズマ種子科学」 - オーガナイザー
國枝 正(奈良先端科学技術大学院大学)、古閑 一憲(九州大学) -
詳 細
人工的雷である「プラズマ」を生物に応用する研究が進んでいる。プラズマで発生した活性酸素による生体応答が分子メカニズムのひとつとして認識される中、自然現象ではありえないような短寿命な分子や機能性分子、電場を与えて対する応答を起こすことができる。一方で、その背景にある分子メカニズムは不明な点が多い。本シンポジウムでは、分子生物学者には馴染みが薄いプラズマのいろはから、植物特に種子を対象としたプラズマに対する植物の応答メカニズムを紹介し、分野融合的に議論したい。
11:15-12:35
- 先端技術で拓く視覚・網膜研究の新時代
Frontiers in visual and retinal science: Advances in Molecular Biology and Cutting-Edge Technologies - オーガナイザー
大津 航(岐阜薬科大学)、高橋 慶(ペンシルバニア大学) -
詳 細
ヒトは外界情報の8割を視覚から得ており、傷害や疾患による視覚障害は人々のQOLを著しく低下させる。光を受容する視細胞は高度に分化・発達した感覚繊毛である。近年、分子生物学的手法や超解像顕微鏡技術の飛躍的な進展に伴い、視細胞の緻密な制御機構の分子基盤が明らかされつつある。本シンポジウムでは、視細胞を主軸とする網膜研究の最新知見に加え、低分子からオプトジェネティクスまで、多岐にわたる視覚障害治療の創薬展開について紹介する。
11:15-12:35
- バイオグリーントランスフォーメーションで拓くCO₂固定の新時代
A new era of CO₂ fixation made possible by bio-green transformation - オーガナイザー
小倉 淳(長浜バイオ大学)、鈴木 道生(東京大学) -
詳 細
バイオミネラリゼーションによって生成される炭酸カルシウムは、二酸化炭素を長期固定しうる手段です。新たな学術的エビデンスを活用し、炭酸カルシウムベースのCO₂固定制度を普及させるために、分子生物学的知見と両面から検討する必要があります。カーボンニュートラルへの貢献を目指し、微細藻類によるCO₂吸収の相乗効果を探りながら、カーボンニュートラル実現に向けた課題と戦略を議論します。産業界との連携、環境分野への応用も議論し、社会実装の具体的道筋を探ります。
11:15-12:35
- 病気とミトコンドリアのクロストーク
Crossroads of Health: Mitochondria and Disease Communication - オーガナイザー
武田 啓佑(大阪大学)、志村 大輔(ユタ大学) -
詳 細
細胞内代謝と分子経路が複雑にクロストークするスクランブル交差点「ミトコンドリア」。そこは細胞内共生を起源とするエネルギー合成中枢としての役割を超えた多機能性と応答性を有している。本シンポジウムでは、生理・病態の観点からシグナル変換装置としてのミトコンドリアの働きと波及効果について、最新の分子生物学的知見を交えて紹介する。夢にときめく学生と、明日にきらめく若手研究者による積極的な発表・議論・交流の場を設けるとともに、ミトコンドリア研究領域への新規参入のきっかけを提供したい。
11:15-12:35
- 脳サイズの生物学と小頭症の病理
The Biology of Brain Size Determination and the Pathology of Microcephaly - オーガナイザー
大隅 典子(東北大学)、星野 幹雄(国立精神神経医療研究センター) -
詳 細
脳のサイズは種によって大きく異なり、その制御機構の解明は発生生物学的にも進化生物学的にも重要な課題であるとともに、その制御不全により小頭症が生じる。本シンポジウムでは、脳サイズを決定する分子メカニズムについて、マウス、フェレット、マーモセット、ヒトなどの脳サイズの異なる哺乳類動物をモデルとした最新の研究成果を紹介する。さらに、その機構の異常によってもたらされる小頭症の病理についても議論する。
11:15-12:35
- ライブイメージングにより解き明かす配偶子形成の仕組み
Revealing mechanisms of gametogenesis by live imaging - オーガナイザー
伊藤 将(大阪大学)、今井 裕紀子(埼玉大学) -
詳 細
配偶子形成は、有性生殖を行う生物が次世代に多様な遺伝情報を安定的に継承する上で必須のプロセスである。近年、ライブイメージングを中心としたイメージング技術により細胞や染色体の動態を可視化することで、配偶子形成の時空間的制御機構が詳細に明らかになりつつある。本シンポジウムでは、幅広いモデル生物種を対象とし、配偶子形成の仕組みについて議論する。
11:15-12:35
- がん三次元培養研究の新展開
A new horizon of cancer 3D research - オーガナイザー
岡本 康司(帝京大学)、後藤 典子(金沢大学) -
詳 細
がん組織のもつ多様性や可塑性などの特性は、抗がん剤の抵抗性や転移能などのがん難治性と深くかかわっており、その理解はがん克服をめざす上で重要である。オルガノイドやスフェロイド等の三次元培養系は、がんの持つこのような特性をin vitroで再現でき、がん研究を行う上で重要なツールとなってきている。本シンポジウムでは、三次元培養を応用した臨床がんの本態に迫る研究についてご紹介する。
11:15-12:35
- クロマチン動態から臨床応用まで広がる転写研究の新展開
Transcriptional Research from Chromatin Dynamics to Translational Insights - オーガナイザー
伊藤 敬(長崎大学)、井上 聡(東京都健康長寿医療センター) -
詳 細
基礎的なクロマチン研究から高度な in vivo アプローチまで、転写調節の最前線について議論します。本セッションでは、クロマチン動態、転写因子、RNAポリメラーゼ II の研究における第一人者が、クロマチン研究の基礎から最新の知見に至るまでを紹介します。また、がんとの関連において、異常なホルモン受容体活性やクロマチン構造が前立腺がんや乳がんの進行をどのように促進するかを取り上げます。特に、老化、加齢性疾患、がん治療におけるクロマチン構造と遺伝子転写の分子メカニズムを掘り下げ、これらの知見が臨床応用に発展する可能性についても議論します。
11:15-12:35
- 美しい脈管ネットワークで決まる臓器機能
Organ function defined by an exquisite vascular network - オーガナイザー
坂上 倫久(愛媛大学)、吉松 康裕(新潟大学) -
詳 細
近年の組織透明化技術と生体イメージングの進歩は、各臓器が織りなす血管ネットワークの全容を明らかにしつつある。それぞれの臓器は、まるで異なる設計図に基づくかのように独自の血管構築を示し、従来知られていた酸素・栄養供給の役割を超えて、臓器特異的な新たな機能の存在を示唆している。本シンポジウムでは、組織固有の美しい脈管ネットワークを紹介し、その構造が紐解く新しい生物学的知見について議論を深める。
11:15-12:35
- 生殖代謝学:環境と代謝による生殖サイクルの制御
Reprometabolism: Environmental and metabolic control of the reproductive cycle - オーガナイザー
林 陽平(東北大学)、前澤 創(東京理科大学) -
詳 細
生殖細胞系列は胚発生期に始原生殖細胞として出現し、成体の長い期間に亘って保持され、次世代個体を生み出す機能を維持し続ける。胚発生から新生児期には母体由来の環境、成体では自身の置かれる環境やライフ時間の経過が生殖細胞や支持細胞の代謝状態に影響し、エピゲノム状態や生殖機能の制御に関わるが、その仕組みを明らかにする研究は端緒についたばかりである。本企画ではこのような研究を生殖代謝学と位置づけ、その現状と展望について議論を深めたい。
11:15-12:35
- エピゲノブリッジ:クロマチン記憶の来し方行く末
Epigenobridge: where chromatin memory comes from and goes to
協賛:学術変革(B)エピゲノブリッジ - オーガナイザー
日詰 光治(埼玉医科大学)、寺川 剛(京都大学) -
詳 細
「クロマチンに残された記憶」。この現象については、その継承原理が不明であるのみならず、その継承が細胞にもたらす影響の範囲についても理解の途上である。本シンポジウムでは、クロマチン記憶に関する多彩な切り口の研究発表を通じて、エピジェネティクスを「分子」から「細胞・個体」レベルまで横断的に理解する“橋渡し”となる議論を期待したい。
11:15-12:35
- 骨格筋を基軸とした運動栄養生物学の新展開
New landscape of exercise and nutrition biology: molecular regulation of skeletal muscle - オーガナイザー
小野 悠介(熊本大学発生医学研究所)、伊藤 尚基(国立長寿医療研究センター) -
詳 細
超高齢社会を迎えた我が国では、加齢に伴う筋量・筋力の低下(サルコペニア)は喫緊の医学的・経済的課題となっている。サルコペニアに立ち向かう手段として運動や栄養が有効であることを示すエビデンスは枚挙にいとまがないが、それらの分子基盤の包括的・統合的な理解は依然として進んでいない。本シンポジウムでは、骨格筋の代謝シグナルやエピゲノム制御、骨格筋の多臓器連関を含む幅広い視点から、サルコペニア克服に資する運動栄養生物学の最新の研究成果を議論する。
11:15-12:35
- 生体の恒常性維持における糖鎖修飾の重要性
Importance of glycosylation on organism homeostasis - オーガナイザー
藤平 陽彦(理化学研究所)、今江 理恵子(東京都健康長寿医療センター研究所) -
詳 細
糖鎖修飾は最も主要な翻訳後修飾であり、修飾分子の正常な構造および機能獲得、細胞間・細胞内でのシグナル伝達、ウイルス感染、免疫応答、がん、老化など、生体の恒常性維持、生体防御、疾患に関連する多くの生命現象において重要な役割を果たしている。本シンポジウムでは、“糖鎖修飾”の変化や異常がどのように“生体の恒常性維持”に影響するのかに関して、気鋭の研究者から最新の知見について発表していただき、その重要性について議論を交わしたい。
11:15-12:35
- TORをトリまく栄養応答の最前線
TOR's Open Door: The Key to Nutrient Responses - オーガナイザー
中津海 洋一(名古屋市立大学)、谷川 美頼(浜松医科大学) -
詳 細
TOR(Target of Rapamycin)は、細胞が富栄養状態や飢餓状態を認識し、応答する過程の中核を担う分子である。本シンポジウムではTORシグナルを基盤に、細胞がどのように栄養環境を感知するのか、また細胞を環境にいかに適応させるのかのメカニズムに焦点を当てる。酵母からヒトまで幅広い生物種における栄養応答の最新知見を紹介し、研究の最前線を探る。
11:15-12:35
- 貪食の多様性と普遍性:生命をかたちづくる見えざる力
Diversity and Universality of Phagocytosis: The Invisible Force Shaping Life - オーガナイザー
津久井 久美子(国立感染症研究所)、小山 隆太(国立精神・神経医療研究センター) -
詳 細
貪食は多様な生物種や細胞に見られる基本的な生物現象であるが、未解明の部分も多い。免疫制御における重要性は良く知られるが、神経制御、個体発生、癌、感染現象、さらには環境中での捕食や共生関係の構築にも深く関わっている。本ミニシンポジウムでは、従来は貪食と関連があるとは考えられてこなかった現象にも焦点を当て、多様な研究領域における貪食の関与を示す。異分野の知見から、生命のダイナミクスを読み解く新たな視点を提供したい。
11:15-12:35
- 次世代ステロイドホルモン研究の最前線
The Frontiers of Next-Generation Steroid Hormone Research - オーガナイザー
馬場 崇(九州大学)、今井 祐記(愛媛大学) -
詳 細
1960年代から90年代にかけて黄金期を築いたステロイドホルモンとその受容体研究は、基礎研究と応用研究の両面で現在もなお目覚ましい発展を遂げています。本シンポジウムでは、ステロイドホルモンが身体の恒常性を制御する仕組みを解明する基礎研究や、関節リウマチ、ガン、高血圧、心血管疾患などの治療戦略に繋がる応用研究の最新成果を紹介します。新たな内分泌制御機構、転写共役因子、リガンドの発見から、臨床応用に向けた展望まで、多岐にわたるテーマを議論します。
11:15-12:35
- 自然環境下における微生物の遺伝子発現の分子機構の理解
Understanding the molecular mechanisms of microbial gene expression in natural environments - オーガナイザー
島田 友裕(明治大学)、小笠原 寛(信州大学) -
詳 細
古くから、微生物はモデル生物として、細胞の仕組みを理解するために、実験室内で研究されてきた。今では、様々な微生物が多種多様な自然環境下で生育していることが知られ、その分子機構を理解することは、現代科学の課題である。本シンポジウムでは、土壌や河川などの自然環境下、また、異種細菌間や動植物との共生や感染における微生物の生存戦略について、遺伝子発現を中心に分子機構の理解を目指している研究を取り上げ、議論したい。
11:15-12:35
- 大規模バイオバンクを基盤とするヒト疾患研究の最前線
Cutting-edge human disease research based on large-scale biobanks in Japan - オーガナイザー
信國 宇洋(東北大学)、後藤 雄一(国立精神・神経医療研究センター) -
詳 細
モデル動物などを使って得られた知見を社会に還元するためには、ヒトの試料・情報を用いた疾患研究が必須である。近年、ヒト試料やゲノム・オミックス情報を保管・管理する複数の大規模バイオバンクが国内で整備されている。本シンポジウムでは、これらの貴重なリソースを利活用した多様なヒト疾患の最先端の研究を紹介し、分子生物学の社会実装、医学への応用を促進する糸口となることを期待している。
11:15-12:35
- 温泉微生物がもつ耐熱細胞外殻の分子機構
Thermostable cell surface mechanics in Thermus thermophilus
共催:ThermusQ研究会 - オーガナイザー
別所 義隆(理化学研究所)、中根 大介(電気通信大学) -
詳 細
高度好熱菌(Thermus thermophilus)は、85℃という高温環境下で生存可能なグラム陰性菌であり、遺伝子操作が可能な好熱菌のモデル生物として、基本生命現象の解明や生化学の発展に多大な貢献を果たしてきた。この微生物では、タンパク質や核酸など、細胞機能に必須の生体高分子が耐熱化しており、構造ゲノムプロジェクトによる網羅的な解析から、分子の耐熱の仕組みが一般化されつつある。しかしながら、細胞が高温環境で生きるということは、分子だけでなく、生命を包む細胞自体が耐熱化している必要がある。ここで、細胞の外殻にあたる細胞膜や細胞壁、さらに細胞の表層に位置する線毛や好熱ファージに注目し、耐熱性に関する最新の知見を議論する。
11:15-12:35
- 老化抑制に資する代謝・ビタミンシグナル
Can metabolic and vitamin signaling prevent aging? - オーガナイザー
堀江 公仁子(埼玉医科大学)、東 浩太郎(東京大学) -
詳 細
現代社会では、偏った食事や化学物質によって代謝作用が変容し、老化が加速してメタボリック症候群やがんなどの疾患が惹起されやすくなっている。本シンポジウムでは、代謝シグナルの調節とビタミン作用が老化の抑制に資することができ、健康寿命の延伸に貢献できるかについて論じたい。
11:15-12:35
- シングルセル解析が拓く病態生理学:データ解析と機能解析のハーモニー
Pathophysiology driven by single-cell analysis: harmonizing computational and experimental approaches - オーガナイザー
山崎 昌哉(がん研究会)、浅田 礼光(ハンブルク・エッペンドルフ大学病院) -
詳 細
近年のシングルセル解析技術革新により、組織発生や恒常性維持、さらに疾患に関与する細胞の多様性が明らかとなってきた。Human Cell Atlasのような網羅的データは蓄積されたが、特定の現象における亜細胞集団の機能解析や重要性の確認は、実験系構築の難しさなどのために依然容易ではない。本シンポジウムでは、新進気鋭の若手研究者を招き、データ解析と機能解析を融合した研究例を紹介する。特に、解析のコツや注意点、さらにどのように介入試験に落とし込むかに焦点を当て、議論する。
11:15-12:35
- 魅惑の骨格筋生物学:健康長寿への新たな旅
Fascinating Skeletal Muscle Biology: A New Journey Towards Healthy Longevity
共催:日本筋学会 - オーガナイザー
鈴木 直輝(東北大学)、青木 吉嗣(国立精神・神経医療研究センター) -
詳 細
骨格筋は人体最大の臓器であり、日常の運動や健康を維持する上で中心的な役割を果たし、また筋疾患のみならず生活習慣病や加齢性筋萎縮においても骨格筋の機能異常が深く関わる。超高齢化社会における健康寿命の延伸のためにも骨格筋の理解は欠かせない。筋疾患やサルコペニアにおける異常タンパク質凝集や組織恒常性維持機構の破綻を分子レベルで多角的に理解し、骨格筋生物学の新たな地平を切り開く。
11:15-12:35
- 進化における革新と生物多様性の源泉としてのデノボ遺伝子誕生
De novo gene birth as a molecular origin of evolutionary innovation and biodiversity - オーガナイザー
末永 雄介(千葉県がんセンター研究所)、Li Zhao(The Rockefeller University) -
詳 細
生物進化においてnoncoding ゲノム領域から全く新規に誕生する遺伝子をデノボ遺伝子と呼ぶ。デノボ遺伝子は酵母からヒトに至るまで広範な生物種で同定され、種としての特徴を創造する。またデノボ遺伝子の寿命は短く、デノボ遺伝子の誕生と喪失が系統内における遺伝的多様性を生み出す。本ミニシンポジウムではデノボ遺伝子を研究する進化学、構造生物学、医学の研究者が一堂に会し、最新の知見を発表する。
11:15-12:35
- 自閉スペクトラム症が示す多様な世界の理解を目指して -動物からヒト、分子から個体、分野横断的な研究の最前線ー
Aiming to understand the diversity of autism spectrum disorder -From animals to humans, from molecules to individuals, at the forefront of cross-disciplinary research- - オーガナイザー
内野 茂夫(帝京大学)、古田島 浩子(東京都医学総合研究所) -
詳 細
自閉スペクトラム症(ASD)は、社会的コミュニケーションの障害や興味・行動の限局化、感覚異常など多様な症状を示す先天的な発達障害である。本ミニシンポジウムでは、ASD者の臨床知見に基づいたヒト型ASDモデルマウスやASD者のiPS細胞とモデルマウスの種をこえた病態検証、ASDを高頻度に伴う結節性硬化症など他疾患からのアプローチなど、分野横断的な研究からASDの最前線の研究トピックスを紹介します。